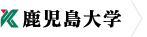専任教員ブログ
コロナ禍と大学教育
高等教育研究開発センターの出口です。
2020年8月現在、世界は新型コロナ・ウイルスの影響下(コロナ禍)にあります。勿論、我が国も例外ではなく、日常生活や経済活動に非常に大きな影を落としています。
学校教育も大きな試練に立たされています。鹿児島大学においては、原則的に対面授業はできず、コンピューターや通信テクノロジー(いわゆるICT)を活用したリモート講義、オンライン/オンデマンド授業が行われています。学校の教職員もICTの開発者も、さらにより良い教育方法やテクノロジーを模索しているのが現状でしょう。
このような状況は、コロナ禍が続く限り変わらないと思われます。そして恐らく、コロナ禍が過ぎ去った後(ポスト・コロナ)でも、この趨勢は消え去らないと思われます。どういうことでしょうか。
従来も、「反転授業」や「調べ学習」など、ICTを活用して学習者が主体的に学ぶような取り組みが学校教育において行われてきました。アクティヴ・ラーニング(主体的学び)が重視される中で、このような学び方は重要なトライアルであると捉えられてきました
トライアルであるということは、それがメイン・ストリームにはなっていない、ということの裏返しでもあります。反転授業に取り組んでいる先生は先進的だと見なされたり、パソコンを活用して調べ学習を行うことは今風だと思われたりして、今もなお学校における教育・学習の中心はやはり教室において先生が行う授業、すなわち講義であると言えます。
ところが、コロナ禍において半ば強制的に、トライアルがメイン・ストリームにされてしまいました。普通の授業でリモート講義が、普通の授業であらかじめ用意された動画を視聴してリモート講義に臨むというリモート反転授業が、当たり前のように行われるものとなってしまいました。
特に、今年大学に入学した新入生は、入学していきなりそのような学修スタイルを強いられたわけです。幸いにして彼ら彼女らは、生まれながらにしてICTと共存してきたディジタル・ネイティヴ世代です。新しい学び方への順応は非常にスムーズでした。また、教職員の側は必ずしもそうではありませんでしたが、試行錯誤と四苦八苦を経て何とか教育活動を展開できるようになってきました。
学生も教職員も、ICTを活用した新しい教育を、新しい学びを、知ってしまったわけです。そして、コロナ禍以前の対面授業等の経験と照らし合わせ、ICTは何が得意で何が苦手なのか、対面でなくてもできる学びはどのようなもので対面でなければ難しい学びとは何なのか、見えてきてしまったわけです。そして、対面授業ICTを組み合わせればどんない素晴らしい教育・学習が展開できるか、経験として分かってしまったのです。
もう元には戻れないでしょう。ポスト・コロナにおいては、新しい学校教育、新しい大学教育が展開されていくことになると思います。それは、学校教育あるいは大学教育のパラダイム・シフトと呼んでも大袈裟ではないかもしれません。
コロナ禍は人類にとって大きな不運であり、それが継続している今はとにかくその収束が最重要課題です。しかし、我々大学関係者はポスト・コロナを見据え、今のうちから新しい大学教育のあり方に備える必要があると思います。