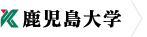専任教員ブログ
コロナ禍を経験しての学会活動
こんにちは。森です。
新型コロナウイルス感染症流行の中の大学授業も3年目の前期が終わりました。前期の私の担当授業は、全て対面の授業と全て遠隔の授業という両極端な構成でした。少人数の授業では、座席位置や学生のディスカッションの時間の制約はありますが、概ね3年前とあまり変わらない授業ができるようになっています。
これに合わせてと言うわけではないですが、私が活動している学会も対面での開催が戻ってきています。学期中に大学教育学会の全国大会に参加しました。私自身も「久しぶり!どうしている?」という会話を研究者仲間としていましたが、至る所で同じような話が繰り広げられていました。この夏休み中は、久しぶりの対面での学会発表も予定しています(とは言え、この感染状況で対面実施の再検討が行われているようです...)。また、11月に3年ぶりに対面で開催される国際会議にも投稿しました。久しぶりの対面開催の国際会議ですが、アクセプトされるかどうか...を含めて楽しみです。
パンデミック対応で、授業のみならず学会や研究活動も、オンラインの良さやオンラインで代替・拡張できることに改めてスポットが当たったと感じています。実際に私も、研究発表に参加した発表者に対し、学会が用意したシステムを通して質問を遅れるサービスを利用して質問を送ったことが数回ありました。対面の学会でしたら、質疑応答の時間は限られていますし、発表後に個人的に話を伺うにしても時間の制約は当然あります。また、同じように話を伺いたい人が多く待っていると結局時間が合わずに...といったこともあります。そういった時間の制約なく、気軽に意見交換ができたことは遠隔発表やそれを支えるシステムの効果とも言えます。
一方で、発表終了後に個人的に話を伺ったり、ディスカッションしたりする時間はやはり大切だったな...とも感じました。例えば、発表後に質疑応答で質問をして頂いた先生のところに行き、名刺を交換して簡単にディスカッションをしたり、その過程でアドバイスを受けたりすることがあります。そのような先生と後に学会等で会ったときに「あのときはりがとうございました!」「あの研究こうなりました!」「論文通りました!」といった話につながったりもします。遠隔発表の場合は、どうしてもこういったコミュニケーションは難しくなったと感じました。
こういったネットワークや場作りの話は、研究の本質とは異なるところではありますが、研究者同士で励まし合ったり、刺激し合ったりすることは、研究を続けるモチベーションの1つです。研究は研究として前に進めつつも、オンライン、対面の良さや、自身がどう参加し、どう振る舞うのか?といったことは改めて考える必要があるなと感じます。
遠隔授業のサポートでなかなか研究に頭が回らない2年ではありましたが、そんな中でもしっかり頑張っている研究者仲間の姿を見ると負けていられませんので、研究室で論文を書く夏を過ごしています。暑い夏が続いていますが、みなさんも熱中症などお気をつけください。