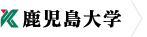専任教員ブログ
FDとは、私が果たすべき役割とは
伊藤です。
何も投稿しないまま5月に入ってしまいました。いろいろあったようななかったような、という感じです。気が付いたら5月でした。今はGWの前半と後半の狭間ですが、後半も終わると、新入生が新入生ではなく大学生になることでしょう。
全学的なFDの推進という職務上の役割にいるため、FD関連のワードや状況について考える機会が多々あります。その中から2つほど。
1つは、授業アンケートです。授業アンケートは既にどの大学でも当たり前に行われるものとして定着していると思います。「学生が教員の授業を評価するとは何事か!」という反応だった時代からすれば隔世の感があるといえるでしょう。
ただ、定着したからこそ考えなければならない問題もあると思います。一教員としての私としては、「そこそこの評価を得られ続けている授業については、授業アンケート結果の活かし方がわからない」と感じています。厳しい意見というのはそんなに出てきません。私が担当している授業の大半が共通教育で、受講生は概ね1年生ということ、あるいは学生の気質そのものが変化している可能性もあるかもしれません。いずれにしても、「満足」「概ね満足」といわれてしまうと、何をどう改善したらよいかのヒントをそこから得るのは困難です。一方で、誹謗中傷に当たるような暴言を書いてくる学生もいるとの声も耳にしており、それはそれで授業改善へのヒントとしては活かせません。
結局のところ問題は、「授業アンケートは授業改善に活かせているのか」という点にあると思います。今までのモデルをそのままやり続けるのが本当にベストなのか、考えるべきタイミングなのかもしれません。
個人的な思い付きとしては、レポートの書き方の指導をするなら、いっそのことそのフォーマットで授業改善に向けた提案レポートを書かせてみたらどうかと考えたりしました。現在の授業の中に課題を発見し、それがなぜ解決すべき課題といえるかを論理的に説明し、その解決に向けた具体的な提案を行うという構成は、レポートとしてよくあるものだと思うのです。現実的に実現可能かどうかは何ともわかりませんが、記名式で論理的かつ建設的な提案をする、それも評価に含む、といった形ができたら面白いのではないかと思っています。
もう1つは、FD委員に対するFDの必要性です。委員会方式で全学的にFDを推進するとなると、毎年のように委員が交代してしまうので、特定の誰かを育てるというのは困難です。それが基本的なサイクルなのだとすれば、委員が交代することを前提としつつ、学部や研究科のFDがより意味あるものになるよう、毎年できることをする以外にありません。そういう中で、立場上学部・研究科等のFDの推進役となる教員に対するFD活動が必要ではないかと思うのです。
その一方、たまたま委員になっているだけの教員の負荷を上げるのもどうかという思いもあります。管理運営業務の増加で研究にかけられる時間が減っているとの指摘は、本学に限らずどの大学にも共通する話ですよね。
だとすると、少しでも効果的かつ効率的なFDの在り方を考え、お伝えするのが私のような立場にある人間が果たすべき役割なのかもしれません。毎年代わる委員に対して毎年そんな話をするのは非効率的ではありますが、そういう在り方を模索する必要もあるのではないかと思っています。
授業アンケートに限らず、FDという概念が定着したからこそその在り方を見直すべき時期なのかもしれません。授業改善という非常に狭義のFDはともかく、組織を、組織が行う教育をより良いものにするためのFDとしてより適切な在り方とは何ぞやという大きな問いに向き合っているところです。