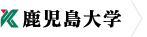専任教員ブログ
進取の精神チャレンジプログラム(一般部門)審査委員会に参加しました
伊藤です。
何だか長いですが、表題の話です。「進取」というのは、自ら困難な課題に果敢に挑戦することを意味することばであり、本学ではこの進取の精神を持った学生を育て、輩出することを目指しています。
進取の精神チャレンジプログラムは、この進取の精神に対する考え方を踏まえ、困難な課題の解決に取り組もうとする学生グループを大学として支援しようとするものです。一般部門と地方創生活動部門の2つがあり、私が今回審査にかかわったのは一般部門のほうです。
基本的に学生支援に関するものなので、これまで私はほぼ無関係でした。「ほぼ」というのは、顧問をしている鹿児島大学ウミガメ研究会(略称「カメ研」)はこのプログラムに何度か応募・採択されたことがあるためです。申請に当たって指導をした記憶はなく、おそらく何をしたわけでもないのですが、一応顧問ではあるので無関係でもないため「ほぼ」無関係だと思っています。
今回の進取の精神チャレンジプログラムで審査に当たっての率直な感想としては、案外まとまったものが出てくるのだな、です。もっと破天荒な、大風呂敷広げるようなものが出てくるかと思っていたので、ちょっと意外でした。
「自ら困難な課題に果敢に挑戦する」というのが進取という言葉の意味するところです。例えば「それはサークルとしての通常の活動ですよね?」という内容で、進取の精神を体現していると思えるかというと、なかなか難しいと感じます。申請者としては、自分(たち)が思う「困難」に挑戦しているのでしょう。ですが、「それは支援があってもなくてもすることですよね?」と審査員に思わせてしまったら、困難に果敢に挑戦しているとはみなされなかったということです。結局は説得力のある書類が出せるか、プレゼンテーションができるかに尽きます。
今回、採択が決まった団体の皆さんには、申請書の通りよりむしろ申請書以上の成果を出していただけることを願っています。また、「条件付き採択」となった団体については、そこで付いたコメントに真摯に向き合ってほしいと思います。審査委員は何も意地悪でコメントを付けているわけではありません。より良いものになるように、また、生じる可能性もあるリスクを可能な限り提言するようにと考えてのコメントです。ひとつひとつにしっかり向き合って適切な対応を考え抜くことで鍛えられる思考力があり、実施事項もレベルの高いものになるはずです。
まずは、年度末の成果報告会を楽しみに待とうと思います。
来年度はカメ研が申請してくるかな?ただ、カメ研が申請してくると、私は顧問なので審査委員からは外れないといけないのかな。私はそれでもいいけれど、担当事務の方に余計な仕事をさせることになるのがちょっと申し訳ないな。