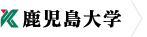専任教員ブログ
IRセミナーで登壇しました
伊藤です。
3週連続で何かしら登壇していますが、今回は学内のIRセミナーで学生調査についてお話しさせていただきました。対面でご参加くださった皆さま、web視聴してくださった皆さまに感謝申し上げます。
これまでもセンターとして教学IRに一定の関与をしてきましたが、4月から教務担当学長補佐という新たな立場をいただき、IRセンターから見ると教学IRの取りまとめ役のような役割を付与されることになりました。私自身がデータ分析するわけではないので実働としてはあまり変わりませんが、分析担当者がデータを利用しやすいようフォーマットを整えたり、これまでバラバラに行われていた活動をつないだり、データ分析ができていないところをカバーする方策を考えたりと、後方支援的にやることができたように思っています。
私の悪い癖で、何かの場に出ると新しい仕事を考え出してしまうため、今回もまた面会の予定と企画の予定を既に作っています。時間が経ってしまうと皆さんの意識から抜けてしまうので、鮮度が落ちないうちに動かないといけないと思ってしまうのです。周囲の方々の仕事も増やすのが申し訳ないですが、増やしすぎないよう配慮はするのでどうかお付き合いください。
今回のテーマと直接関係あるといってよいのかは迷うところですが、全学的なFDの牽引役という役割を担うセンターとしては、授業アンケートの今後を考えなければと考えるようになりました。授業アンケートが日本の大学教育に取り入れられるようになってからかなりの年数が経過し、どの大学でも定着したと思います。その一方、実施することだけが続いてしまい、十分活かせていないのではないかという問題も顕在化してきています。授業アンケートの形骸化といえばよいでしょうか。
授業アンケートは、教員の側からすれば各学期末に担当科目数分、本学でいえばmanabaを使うため、集計結果だけをすぐに確認することができます。自分で集計するわけではないので、教員個人としては莫大な負荷がかかるものではないでしょう。
しかし、学生の側からすれば、学期末に受講科目数分一気に回答を迫られます。試験や期末レポートも抱える中、10科目以上の授業アンケートともなれば、まじめに回答する学生ほど調査疲れを起こしてもおかしくはありません。それに、授業アンケートは一般的に学期末に行われるため、頑張って回答しても改善の利益を受けられることはありませんし、そもそも改善されたかどうか、自分の意見が反映されたかどうかを確かめる機会さえありません。その状況の中で頑張って回答せよといっても、なかなか難しいところもあると思うのです。
だからといって授業アンケートをやめるという話をするつもりはありません。ただ、様々な学生調査も走っている中、いずれにおいても一定の回答率を確保するためには、負荷を減らす方策も考える必要があります。学生だけでなく教員の側についても、組織としての教育改善に活かしてもらおうとするならば、管理運営業務が拡大していく中で負荷を減らすべきところもあると思います。0か100かではなく、効果的かつ効率的な落としどころを模索していければと思います。
おそらく教学IRというのは、この「効果的かつ効率的な落としどころ」を考えないといけないことの1つですよね。まだまだ模索は続きます。