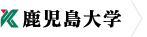専任教員ブログ
鶴丸高校で講演してきました
伊藤です。
昨日、鹿児島県立鶴丸高校にお邪魔してきました。県内トップの公立高校ですね。岐阜県出身者としては、「県名を冠した高校がトップ校じゃないのか」と思いますが、鹿児島県の場合、鹿児島高校は私立です。いろいろなパターンがあるのですね。
さて、今回お邪魔したのは、「総合的な探究の時間」に関する講演が目的でした。生徒さんたちに対し、この科目の意図・目的とは何なのか、大学での学びとどうつながるのか、大学は"特にこの科目に"何を期待しているのか、といったお話をさせていただきました。
本学では全学必修科目として「初年次セミナー」を開設して8年になりますが、「初年次セミナー」で学生に見られるよくある問題と、事前に伺った鶴丸高校生が「総合的な探究の時間」で遭遇する問題は、かなり重なっていました。だとすれば、それらをできるだけ高校生の間に解決してもらえれば、大学での学びがより有意義になるのではないかと思っています。
「初年次セミナー」で最も問題になるのは、適切な問いが立てられないことです。調べればわかることを問いにしても、調べたらこうでしたという報告しかできません。そんなことは求められていないんですよね。あとは、袋小路に入り込んで行き詰まり、いつまで経っても問いが立てられないという学生も毎年います。どこかで決断しないといけないんですが、考えすぎて身動きが取れなくなってしまうタイプですね。そのテーマで活動が進められるかどうかは、調べたり、書いたりしないとわかりません。基本的にこの段階では基礎レベルの知識も十分備わっていないテーマを取り上げようとしているのですから、考えているだけでは適切かどうかを自力で判断するのは難しいと思います。だから、とりあえず調べてみて様子を探ったほうが良いわけです。
「総合的な探究の時間」に積極的に取り組み、大学の教員が指導や支援に参加している高校もある一方、現実問題としてそこに労力をかける時間や人員がない高校もあるでしょう。しかし、大学に入ってしまうと、どんな高校を出てきたかは問題にされません。探究活動について一定程度気スキルを持った学生と全くそうでない学生とが同じように扱われるわけですから、後者にとっては少し後ろからスタートせざるを得なくなってしまいます。それはできるだけ避けるべきものだと思います。
となると、大学にできることとしては、高校の先生方や高校生自身が、探究、ひいては研究の専門家である教員にアクセスしやすくし、できるだけサポートしていくことかと思います。高校に行って生徒を指導することだけが大学にできる支援ではありません。今回の講演がどこまで役に立ったかはわかりませんが、「そもそも『総合的な探究の時間』には何が期待されているのか」といったそもそも論を伝えることも支援になり得るものです。誰に相談したらよいかわからないと困っている生徒や先生方に対して窓口を開き、ニーズを踏まえて適切な教員につなげることができれば、助かる人はたくさんいるのではないでしょうか。
私の悪い癖で、刺激を受けると新しい仕事を考え出してしまいます。常に自分の仕事を増やす覚悟は持っていますが、自分1人で完結する仕事などめったにないので、周囲の皆さんには申し訳なく思っています。それでも、大学にとっても高校にとってもより良い状態につながるようなことができればと願って、できることから始めていきたいと思います。
今回は、貴重な機会を与えていただき、鶴丸高校関係者の皆様に感謝申し上げます。