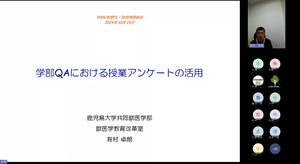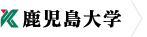専任教員ブログ
FD・教学IR研修会を開催しました。
伊藤です。
表題にあるのは昨日の話です。教学IRはそのFDに活かしてこそ、という思いで、このような名称として企画しました。ご講演いただいた有村先生、ご参加いただいた皆様、運営をサポートしてくださった教育企画係の皆様、ありがとうございました。
授業アンケートをテーマとして企画した今回の研修会講師は、共同獣医学部獣医学教育改革室室長である有村卓朗先生でした。共同獣医学部ではかなり積極的に授業アンケートの結果をカリキュラム改革に繋げていたことから、その実践についてお話しいただきたいとお願いしました。
授業アンケートは、今やどの大学、どの学部でも行われている取り組みの1つですが、その一方で形骸化も指摘されています。ここでいう形骸化とは、授業アンケートは実施され、集計されているものの、個々の授業改善に活かしている教員もいればそうでない教員もいる状況がずっと続いていること、評価の高い教員の場合、活かしたくても活かしようがないこともあること、そして何より大きな問題は、個々の授業改善を超えた組織としての教育改善、カリキュラム改善に活かせていないことを指しています。ぎゅっと圧縮していえば「授業アンケートを取ってはいる」だけの状態になってしまっているといったところでしょうか。
共同獣医学部の場合、EAEVEという非常に大きな"外圧"があるため、組織的な教育改善に繋げることは必須となっています。しかし、そうした"外圧"がなくても、学生の声を収集する以上、それを組織として活かすことは必須であるべきものだと思います。有村先生のお話にもありましたが、学生も教育改善に大きく関与する重要な存在です。学生が着実に能力や技術を身につけて社会に出ていけるようにすることが大学教育の目的ですから、そうなるようにカリキュラムを改善し、具体的な教育活動を改善するのは当然といえるのではないでしょうか。その意味では、個々の授業改善も、単なる学生の満足度の問題ではなく、学生の能力を伸長させることができているかという観点から見直す必要があると思います。
事後アンケートの中では、こうした取り組みを行う場合の教員の負担増を懸念する声もありました。人が減る中、業務はむしろ増えているため、懸念する思いもわからなくはありません。
私の立場でいえることとしては、授業アンケートであればすべての授業で毎年実施しなければならないかを考え直してみることや、質問項目の立て方や内容を見直してみることで減らせる負荷もあるのではないかということです。特に、予算も人もない中で新しいことを始めようとするのであれば、スクラップ&ビルドの発想が必要です。授業アンケートはやってさえいればよいわけではないので、「適切な教育改革・教育改善を行うために収集すべき学生の声とは何か」を今一度考える機会となればと願っています。