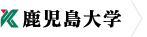専任教員ブログ
2040年の大学の定員充足率
伊藤です。
標記の件について、12日に行われた中央教育審議会高等教育の在り方に関する特別部会で推計値を文科省が示したことが報道されていますね。現在の入学定員規模が維持された場合、2040年の大学の定員充足率は7割程度、2050年には6割程度になるとのことです。
この数値は、どう受け止められるものでしょうか。私自身は「その程度で収まるのか」と感じました。そもそも7割というのはすべての大学の定員充足率をならしたときの話です。実際には定員を充足するあるいは充足に近い状況の大学もあれば定員割れの程度が甚だしい大学もあるので、2極化がより深刻になるということですよね。その差のつき方をイメージすると、平らにならしたら7割というのは案外多くとどまるのだなと私は感じました。
特別部会では答申案も示されていますが、むしろこちらの方が気になりました。間違っているとかおかしなことをいっているとかいうことではありません。そういう次元の問題ではなく、これまでの延長戦のようなことを述べていて果たしてどれほどの意味があるのだろうと思ったのです。
大学の中にいて、教育改革だのなんだのにかかわる立場で仕事をしていると、18歳人口が減ることは誰もがわかっているとしても、対象とする学生の年齢を大転換するとか、教育の目的を変革するとかいったことがいかに難しいかということも実感するようになります。
2020年度からのコロナ禍対応での遠隔授業でも何とかなったことを考えれば、やればできない話ではないでしょう。しかし、あれは自分たちの意志とは無関係にやらざるを得ない状況に直面したからこそできたことであり、自発的にそのような教育のフォーマットの転換ができたかというと、おそらくそうではなかったと思います。
転換や変革の難しさとはそういう意味で、今いる教職員にこれまでの働き方を全部変えろと誰が言えるか、そういう方向に引っ張っていけるリーダーシップを発揮できる人はいるのか、具体的な在り方の設計図を書ける人間はいるのか、といった点で難題山積、果たしてできるものなのかと思うのです。
2040年というと、私は定年の年齢が今と変わらなければギリギリ教員として仕事をしているであろう年齢です(定年の年齢が国立大学より一般的に高い私学に移ればまた別の話です)。定員充足率7割という日本の大学界を取り巻く状況をどこまで自分事と捉えられるか、自分事と捉えて大学の、大学教育の在り方の大転換に関わっていけるかと考えると、こういう立場で仕事をしているので考えろと言われれば考えますし、転換そのものにさしたる抵抗もありません。ですが、本学に限らず執行部を構成されている皆さまは確実に自分より年上であり、自分たちの後の世代が直面する事態の話になるわけです。その状況で大転換の指示を出すというのは、とても責任の重い判断です。
以前も書きましたが、私自身としては、大学進学率は今より上がってもいいと思っています。しかし、その一方で今の大学数がベストではなく整理すべき大学もあるとも思っています。答申案では縮小・撤退への支援という項目もありましたが、ここに書かれているようなことで撤退の判断ができるだろうかというと疑問です。卒業生との関係や地域のニーズなど、様々な要素が絡む話だからです。
答申案の記述がこれまでの延長線上にあると感じたことが私の疑問の核になるわけですが、定員充足率7割といった事態を避けようとするのであれば、これまでの延長線上ではなく、全く違う角度からボールを投げるような、そういった発想の転換が必要なのではないかと感じたところです。