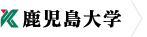専任教員ブログ
令和6年度FD・SD合同フォーラムを開催しました
伊藤です。
標記の件について、開会挨拶をいただいた志學館大学学長の飯干先生、ご発表いただいた志學館大学・杉山先生、鹿児島純心大学・久木田先生、第一工科大学・萩原先生、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。閉会挨拶をしてくださった本学の有倉理事、開催を全面的にサポートしてくださった教育企画係の皆さんにも感謝いたします。
今回のテーマは「授業アンケートの今後を考える」でした。実は、先月実施したFD・教学IR研修会でも授業アンケートを取り上げています。その際には授業アンケートを組織的なカリキュラム改善に繋げているという共同獣医学部の先進事例を取り上げました。それに対して今回は、「先進事例だから」というスタンスではなく、それぞれの勤務校での取り組みを率直にお話しいただくことで事例を共有し、自分たちのところで活かせるところを活かしていくためのヒントを得てほしいと考えて企画しました。
私自身がこの機会に考えたこととしては、主に2点あります。
第1に、学生へのフィードバックです。授業アンケートの結果を受け取った教員にその内容に対するコメントとその後の改善計画を作成して提出させるというのは、多くの大学で行われていると思います。その授業改善計画書について、第一工科大学では学生さんも閲覧可能にしているとのことでした。これはなかなかできることではないのではないでしょうか。自分が本学の委員会で提案することを考えると...炎上する未来が見えます。考えるだに恐ろしい。私個人はそれでも全く問題ないのですが、教員の合意形成ができるかというと非常に疑問ですので、それができているというのはすごいことだと感じました。
授業アンケートは大抵最終回に行うので、回答した学生は自分の回答がその後の改善に反映されたかどうかを知ることができません。次年度改善したとしても、そのことを耳にしたり、改善の成果を享受したりできるのは次の年度の学生です。ですから、回答した学生自身が、自分の回答を教員がどう受け止めたかを知る機会として、せめて授業改善計画書を公開するという方法があっても良いのではないかと私は考えています。
第2に、誹謗中傷対策です。そもそもそんなコメントが学生から出てくることが非常に残念なのですが、現実にはそういうことが起きます。ある特定の授業にだけ起きるということもなくはないですが、どちらかというと特定の学生があちこちで引き起こすというパターンのほうが多いのではないでしょうか。
誹謗中傷対策という点では、社会一般のSNSの問題と同じだと思います。匿名であるかのように思えても個人は特定できるのだから、自分の発言に責任を持つべきだという点でも共通しています。学生が、無記名で書き込めるシステムを使って授業アンケートに教員に対する誹謗中傷を書き込んだとして、それが匿名だと思い込んでのことであるとしたら、授業担当者はともかく管理職が学生を呼び出して指導するというのが一般的でしょうし、それも必要だと思います。
ただ、個人は特定できることを理解したうえで、あえて誹謗中傷を書き込む学生がいた場合、この学生にはどうすべきなのでしょうか。呼び出して指導するとして、何をどう指導するべきなのか、ちょっと考えさせられました。難しい。
授業アンケートについて、個人的には「そもそもこれ必要?」とかいった話もしてみたい気もするのですが、それはやるのはなかなかハードルが高いです。全部自分でしゃべり倒す場であれば気軽ですが、他大学も巻き込む場で掲げるべきテーマなのかというとちょっと疑問です。そういう疑問を持っている人かつ面倒くさいだけというような意見が提示できる人を見つけ出さないと企画できないと思うからです。
どういうテーマを掲げ、どういう場を設けるか、来年度に向けてまた改めて考えてみようと思います。