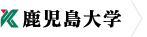専任教員ブログ
「学長と学部新入生との懇談会」に参加しました
伊藤です。
昨日の話です。参加してくれた1年生の皆さん、ありがとうございました。人が話している場面には日常的に遭遇していますが、明らかに緊張している様子を見る機会はあまりないので新鮮でした。学長を目の前にして自分の考えを述べるわけですわけですから、緊張して当然なのかもしれません。
さて、そんな懇談会で私が考えたことは「入学直後の新入生に対するケアはどこまで行うべきか」です。
途中で教育担当理事も言われていましたが、私が学生だったころと比べても、大学は格段に新入生に親切になったと思います。履修登録の仕方も丁寧に説明しますし、提出された課題にコメントを返す教員も増えました。
それでも、新入生にとって過去との比較には意味はなく、今自分の目の前で起きている状況だけが問題です。履修登録で困らないようにしてほしい。レポートの書き方は教えてほしい。困ったときにはすぐに相談できる相手がいてほしい。要望としてはわからなくはありません。
ただ、転ぶ前に手を貸してとにかく転ばないようにするというのが果たして教育的に適切なのかというと、疑問を感じます。息子を見ていて実感しますが、手を貸したほうが早い場面が多々あります。結果として時間もかからないし、助けてほしいとおもっているのですから助けてもらえて満足でしょう。
それでも、手を貸すばかりでは自分でできるようになりません。いつまでも手を貸せるわけではないので、いずれ自立しなければいけないのだとすれば、時間がかかっても、「手伝って!」と泣かれても自分でさせなければならない場面は必ずあります。履修登録やレポート作成をそれと比べるのは違うという意見もあるでしょうが、自分でやってみることでわかること、できるようになることは必ずあると思うのです。だからこそ、果たしてどこまで大学が組織として面倒を見るべきか、悩みどころです。
私は大学生の書く力にずっと関心を持っていますが、どこまで授業という枠組みで教育すべきか、まだ結論を出せずにいます。組織としてどこまでケアをすべきか、大学はどこまで親切にすべきか、難しいなと改めて感じました。
私は高校の出前授業に伺うと、「大学は高校までと比べて不親切なところだ」と言っています。卑下しているわけでもなければ、批判しているわけでもありません。卒業したら社会に出ていく最終段階の教育機関としてある程度不親切でいいと思っていますし、親切にしてもらって当たり前だと思わないでほしいからです。提出物を出さなかったら先生から声をかけてもらえることも、担任の先生が自分の状況を把握してくれていることも、決して当たり前ではないのです。高校までの先生方がどれだけのことをしてくれていたのか、気付いてほしいと思っています。大学に進学した人たちだけでもそのことに気づいてくれたら、「ブラック労働」と揶揄される教員のしんどい状況について、もう少し社会が課題意識をもって現状改善を後押ししてくれるのではないかと、少しだけ期待もしています。
こういうイレギュラーな機会で考えることや広がる世界があるのが楽しいですね。貴重な機会をありがとうございました。