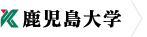専任教員ブログ
日本コミュニケーション学会九州支部大会で講演しました
伊藤です。
11月30日の話です。お声がけいただいた上土井先生をはじめ、ご参加くださった皆さまに感謝いたします。果たして期待に十分沿えたかは非常に心もとないですが、私自身はとても勉強になりました。
私に与えられたミッションは、コミュニケーションに関心を持つ皆さまに対し、生成AIに関して、大学教育あるいは教育改善といった文脈から話をする、というものでした。書いていてもなかなかアクロバティックだなという気がしてきます。実際、お話をいただいた時点で若干フリーズし、「私でよいのですか?」とその後も含め幾度もお尋ねした記憶があります。
やるとなればそれなりに腹はくくりますが、そうはいっても考えなくてもそれなりの話ができるようなテーマではなく。だからこそ勉強になったわけですが、何をどうお話したものかについては、これまでFDのために呼んでいただいた講演よりも頭をひねりました。
そもそも確定していることが少ないので何をどうお話したものかという定型がないのが今の生成AIをめぐる状況です。私はもちろん生成AIを専門とするわけではありませんし、かといって自分の仕事と絡めて考えても、まだ「こんな形で生成AIを使うと教育・授業がよくなりますよ!」といえるようなものでもないわけです。私がこのテーマでいうべきことは何か、核となるメッセージ(テイクホームメッセージといわれるものですね)は何かからして手探り、というのは久しぶりの経験でした。
ChatGPTが日本で知られるようになったあのときのインパクトを考えると、今は報道も減り、なんだか落ち着いたかのようにも見えます。しかし、そんな中で「生成AI」というワードを目に耳にするのはどんなときかというと、声優の方々が自分たちの声を勝手に使わない権利を求めているといった、使い方よりはそれに伴って生じている著作権等に関する問題の場合が少なくありません。
講演でもお話しましたが、生成AIと大学教育というワードを掛け合わせたときに出てくる論点として、ひとつは盗用レポートですが、もうひとつ重要な論点としてこの著作権等の権利をめぐる教育というのがあると思います。前者についても語り始めれば長いですが、それは今回は置いといて、問題は後者です。
生成AIというものが新しすぎて、当然といえば当然ですが法整備が追いついていません。まだまだ未確定の部分が多い生成AIに対して、積極的に使ったほうが良いという人もいれば懐疑的な人もいます。ただ、実際はそんな明確な二分法で語れるものではないのではないでしょうか。
私はというと、とにかく使って見ないことには何もわからないから、まずは使ったほうが良いと基本的には考えています。批判するにしてもなんにしても、見たことも触ったこともないでは説得力に欠けると思うからです。
しかし、実際に問題が起きている通り、生成AIが学習データとして用いた膨大な量のデータについて、その利用は果たして認められていた
のでしょうか。生み出されるものについて、利用される文なり声なり絵なりは、果たして利用を認められたものなのでしょうか。そうではないから声優の方の訴えが起きているわけです。そういったことを考えると、果たして使うことを推奨して良いのか、自分でも決めきれないのが正直なところです。
講演でも答えを示したわけではなく、むしろ参加者の方々それぞれに考えていただきたいと思っていたところではあるのですが、改めて生成AIとどう向き合えばよいのか、考える機会になりました。