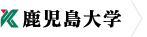専任教員ブログ
年始の大学関連ニュース
伊藤です。
2025年となりました。仕事始めから1週間経ち、既に年始の雰囲気はありません。というか、曜日の巡りの関係で仕事始めが6日でしたが、「今年はゆっくりだなあ」と感じました。4日からとか、珍しくなかったからですね。
さて、表題についてですが、この週末に2つ報道がありました。
1つは、法政大学での学生による学生傷害事件です。なぜ教室にハンマーがあったのかに疑問を感じましたが、それは些末なこととして。
詳細については情報がないので何とも言えませんが、学生が学生に危害を加えるということはあり得ないことではないですし、今回は特に授業中に事件が起きたということで、もし自分が担当している授業中だったらと思うと考えさせられるやら何やら。危害を加えている学生を止めに入るべきだったのか、しかし丸腰でそれができるのか、しかししかし、学生を守るべき立場なのではないか、などなどです。
もう1つは、東京女子医科大学元理事長逮捕です。既に捜査が入ってからかなりの時間が経過しているので、それなりの証拠が見つかっているのだろうと思うのですが、それにしても。
18歳人口が減少する中、私大の多くは経営的に厳しい状況に落ちいているのでしょう。医大の場合、一般の大学とは事情が異なるところがあるのかもしれませんが、だからといって経営的に全く何の問題もないというわけでもないでしょう。
それでも、教育は金銭的メリット・デメリットでは測れない部分がどうしてもあります。学生がより豊かな、より質の高い教育を受けられるようにするにはお金が必要です。さらに医大あるいは医学部の場合、大学病院として社会的に担う役割があり、それは金銭的利益に変えられるものではありません。利益率が低いからといって放棄して良い役割ではないでしょう。そういうせめぎあいは、経営者と教育者あるいは医療者との間で常に存在するのだろうと思います。
事件そのものへの関心ももちろんありますが、先の事前と同様に、こうしたニュースを耳にすると考えさせられることが多いです。こちらのニュースの場合は、大学の役割やカリキュラムとして何をどこまで補償すべきあるいはできるか、ということを考えました。本学に限ったことではないと思いますが、教員も職員も減っています。学生定員は減らしていないので、同じ数の学生に対してより少ない人数で教育等を施していることになります。経営的に厳しい以上、人件費を削るしかないのだろうということも推測が付きます。それでも、果たしてこれで良いのか、ある程度までは仕方がないとしても、底が見えないままこの状態が続くのだとすればいずれ大学教育は質が担保できなくなるでしょう。だとしたら、最低限大学が守るべきラインとはどこなのだろうかと考えたり。
法政大学の事件の背景についてはまだわからない点が多々ありますが、容疑者はいじめを受けていたと主張していると報道されています。それが事実かどうかはともかくとして、人間関係のトラブルというのは学生間で少なくないですし、そのケアの一端を教職員が担わざるを得ない場面も出てきています。これまでにはなかったような仕事が学生に関連して生じている部分も確実にあります。
書類作成や評価対応などの負荷増大についてはこれまでにも報道されたことがあった気がしますが、減少する一方の教職員は、教育や学生指導についても以前より高い負荷を抱えています。心身に不調をきたす教職員も現実に出てくる中、大学は、大学を取り巻く環境はこのままで良いのだろうかと改めて考える、まったくもって明るくない2025年最初のブログでした。