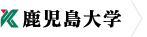専任教員ブログ
中央教育審議会から答申が出されました
伊藤です。
2月21日に新たな答申が示されました。
【我が国の「知の総和」向上の未来像~高等教育システムの再構築~(答申)(中教審第255号)】
立場上は教育に関する部分が気になるところですが、基本的にはこれまでの流れの延長線上だなという印象です。
それでもあえて気になるところを言うと、まずは「文理横断・融合教育」でしょうか。こういう言葉は以前からたびたび示されてきましたが、どこまで理解されているのかというと疑問を感じます。あるテーマや課題について、人文系の知・社会科学系の知・自然科学系の知それぞれの見地から検討し合うというのであればわかりますが、例えばこれが、様々な専門分野の教員がそれぞれに自分の専門の話をしているだけ、学生はいろいろな話を聴くだけであれば、それは「横断」でも「融合」でもないと思うのです。「横断」や「融合」を本当にさせようとすれば、結構大変な話です。鹿児島大学のような総合大学であれば、やり方次第で学内でなんとかできるところもあるでしょうが、単科大学だったらどうするんだろうと思ったりもします。どこまで本気でやるかという話に縮小されてしまいそうで、どうなんだろうなと感じています。
あとは、概要の方には「在学中にどれくらい力を伸ばすことができたのか等を含む教育の質を数段階で評価する新たな評価制度への移行」との文言が見られました。認証評価制度の見直しは、していただければありがたいと思うところです。ただ、果たして学生の能力の伸びを的確に評価し得るのだろうかという疑問も感じます。測れるのはごく一部、それもそのとき測れるものしか測れないという限界がありますよね。果たしてそれを測ったところでどれほどの意味があるのだろうか、意味があるのかどうかわからない業務がまた発生することにはならないだろうかという不安を覚えます。
最近他の先生から言われて印象的だったのは、すでに書いた気もしますが、「しなくてもいいことを教えてほしい」という叫び(?)です。管理運営上しなければならないことは増える一方、教育についても、学習成果が上がったことを示せというオーダーに真面目に応えると、上がったといえることを探し出すとか上がったといえるような取り組みをわざわざするといった話になりかねません。それでいいんだろうかと思います。自分の職務上の役回りに迷うところです。教育改善には取り組んでいただきたいものの、評価に対応するよう文書を残してほしい、チェックをしてほしいといったお願いをする段になると、それは本質的には教育改善のためじゃないよなと思うわけです。
他にも気になる点はあるのですが、とりあえず自分の主業務との関係ということでこの辺で。