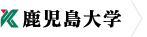専任教員ブログ
「学長と学部卒業予定者との懇談会」に参加しました
伊藤です。
昨日開催された標記の件、今月をもって卒業する各学部代表者の方々の話を聴く機会を得ました。以前、「学長と学部新入生との懇談会」にも参加させていただきましたが、卒業予定者となるとやはり成長を感じました。話す内容も話し方も、ですね。もちろん、ある程度準備してその場に臨んでいただろうとは思いますが、その場で振られたときに返す言葉のレベルが上がるのだと感じました。
印象的だったことはいくつかありましたが、その中で2つほど。
1つは、「総合大学の価値」です。本学部には9つの学部があるのですが、共通教育中心の初年次はともかく、それ以降はどうしても所属学部に閉じがちになります。特に、桜ヶ丘にある医学部・歯学部や下荒田に1学部だけの水産学部の場合、郡元との交流の機会は激減してしまいます。
こういう話になると、どうしても学生間の交流に意識が行きがちです。ですが、昨日の参加者から出されたのは、所属学部以外の学部の教員との交流についてでした。異なる専門性の教員からの助言が受けられることの意義を実感できたというのは、とても価値あることだと思いますし、そこまで行きついた彼女の行動力には頭が下がります。所属学部の教員にコミュニケーションをとることでも、決して容易ではないでしょう。それが、日ごろ交流のない他学部教員が相手ともなればなおさらです。
大学の教員は、確かにクセのある人が若干多いかもしれませんが、学生が相談に来ているのに足蹴にするような非常識人ではありません(と信じたいです)。「助けてください!」と学生から言われれば、できることはしようと思う教員が大半のはずです。それでも、あったこともない教員にアクセスするハードルは低くないでしょう。授業であればオフィスアワーを示していますが、それだけで十分なのかは考えどころです。
教員が、自分が直接指導している学生だけでなく、もう少し幅広く学生の声に耳を傾け、話を聴く機会を設けるために何ができるか、何をすべきか、改めて考えてみようと思います。もちろん、教員もどんどんハードワークになっているので、過労にならないような配慮も一方で必要ですけどね。
もう1つは、留年という経験です。参加者の中に経験者がいたのですが、必ずしも留年はネガティブなことではないと私は思っています。もちろん、学費のかかる話なので積極的に留年を進めるつもりはさすがにありません。ただ、大切なのはその経験を自分の中でどう咀嚼し、自分のその後にどう繋げていくか、自分の人生やキャリアにどう位置付けていくかだと思います。
アイデンティティとは何かという定義はいろいろあると思いますが、自分に対して語る自分のストーリーだと今のところ私なりに考えています。留年した場合、そのことを自分に対してどう語るか、どう説明するか。その過程で自分なりの落としどころを見いだせれば、それはそれなりの意味のある経験にできるのではないでしょうか。今回の参加者であった彼は自信を持って自分のストーリーを語っており、その姿からきっと彼なりの落としどころを見出したんだろうなと感じました。一般的でなくても、他人とは違う進み方であっても、自信を持って語れる道であってくれることを願いたいと思います。
こういう場に参加させていただくことでいつも宿題をもらうことになりますが、今回は宿題だけでなく、素敵な卒業予定者の姿を見せていただきました。そんな皆さんに感謝したいと思います。