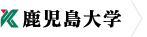専任教員ブログ
「鹿児島大学高校生先取履修科目と高大接続に関するフォーラム」に参加しました
伊藤です。
一昨日の話になりますが、標記のフォーラムに参加しました。企画いただいた理学部長・小山先生、お話くださった理学部長補佐・中西先生、農学部長・寺岡先生、工学部長・木方先生、貴重なお話をありがとうございました。
対面と遠隔のハイブリッド開催だと、学内でも対面参加の方はどうしても少なくなってしまいますね。フォーラムの内容を把握する上では全く問題ないのですが、その前後に参加者同士で話をする機会も結構重要だと思います。今回は、高校から参加くださった何人かの先生方とお話できたこと、あとは、発表者である4人の先生方とお話しできたのが良かったです。同じ大学で仕事をしていても、なかなか直接お会いする機会ってないんですよね。
さて、今回のフォーラムで考えたこと。まず、本題は先取履修科目だったのでそこからいうと、本学の学生さんは何かしら関与しているのかな?授業を受ける一受講生という立場以上のかかわりはあるのかなという点が気になりました。
自分が高校生だったころとは状況が大きく変わっているので、高校生がリアルな大学の姿、授業を知る機会は増えていると思います。どの大学でも積極的にオープンキャンパスを行っていますし、イベント的な大規模なオープンキャンパスだけでなく、通常の授業日に大学を開放するタイプの企画も拡大しています。
その一方、そうした企画において、参加者である高校生と大学生とが積極的に関わる機会があるかどうかで、高校生が知ることのできる「リアルさ」が変わると思います。オープンキャンパスで活発に活動している学生の姿は良いロールモデルになるでしょう。その延長線上で、先取科目を履修する際にも、サポーターとまではいわないまでも、積極的に高校生をサポートする学生がいたらより効果的な学びになるのではないかと思いました。もちろん、そうしたサポートを望まない高校生もいるでしょうから、押し付けるべきではないとも思いますが。力加減は考えどころですね。
もう一つ考えたことは、高大接続というよりは高大連携なのかもしれませんが、高校「総合的な探究の時間」(以下、「探究」と略します)への大学の関わりです。本学には初年次の全学必修科目として「初年次セミナー」というのがあります。前期のⅠはグループでのプレゼンテーション、後期のⅡは個人で長めのレポートを作成し、その過程で様々なアカデミック・スキルの修得を目指します。このⅠのほうで、高校での「探究」での学習経験差が拡大しているように思われます。SSH(Super Science High-School)など、「探究」で非常に積極的に指導をされている高校がある一方、そうではない、あるいはそこに力をかけられる状況にない高校もあるとすれば、学習経験の差は高校生本人の問題ではなく、それでも大学での学びのスタート時点で差が開いてしまうことになります。大学1年前期の成績が卒業時の成績と相関があるということは本学に限らず多くの大学で明らかにされていることを考えると、この差は何とかする必要があるのではないかと考えています。
大学がそうした学習経験差を埋めるためにできることとは何か。例えば教員研修で積極的に指導法について取り扱うなどが考えられます。また、そもそも相談したいことが生じた場合の問い合わせ窓口を設置しておくことも重要でしょう。いずれもそれだけで十分ではないかもしれませんが、何もしないよりはずっと良いと思います。高大連携を通じて「探究」を充実させると同時に、そこから接続した学習を大学でできるようにすることで、「探究」に対するモチベーションを上げることもできるのではないか。そんなことを考えながら、諸々動こうと思っています。
相変わらず何かの企画に参加すると新しい仕事を生み出す癖が治りません。ある種の職業病だと思われます。