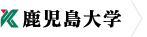専任教員ブログ
女性管理職ネットワーク交流会に参加しました
伊藤です。
標記の件、昨日行われました。そもそも女性管理職が限られているので、参加者数が限られているのは当然といえば当然ですが、それでも小さいながらもネットワークが築かれることには意味があるので、参加できて良かったです。
本学の場合、第4期中期目標・中期計画において、女性研究者在籍比率23%以上、教授・准教授に占める女性研究者比率15%以上、女性研究者採用比率30%以上を掲げています。この数値が高いと思われるのか低いと思われるかはその人がいる環境によって異なると思います。私自身は、「高い!」でも「低い!」でもなく達成できるものなのかがそもそも判断しづらいというのが正直なところだったので、昨日実際の達成状況を見せていただき、「これはなかなか大変だ」と確認した感じです。
私は教員としてちょっと特殊な働き方をしているので、私から見える景色も一般的な教員とは違うところがあると思っています。
主担当組織においては、比較的女性研究者比率が高いので、女性の姿を目にする機会も多いです。ただし、上位職に限定すると必ずしもそうとは言えないとも感じています。
その一方、私が参加している全学委員会の場合、圧倒的に男性教員で成り立っています。全学部・研究科から1人ずつ教員が出てくると9学部+9研究科で計18人になり、それにいくつかのセンターからも参加者がいると合わせて20人強になりますが、全員男性ということもありました。それが珍しいというわけでもなく、逆に自分以外に女性教員が3人とかいると珍しいと感じるような、そんな感覚で過ごしてきました。全学委員会の委員は大抵教授なので、そのことも男性の出現率が上がる要因のひとつなのでしょうね。
女性研究者採用比率を上げるということも積極的に行われてはいるので、今後はもう少し変わっていくのかもしれませんが、早々すぐにこうした「景色」が変わるかというと、残念ながらそんなわけにはいきません。今の大学事情として昔と比べると昇格は容易ではなくなっていますし、採用もそう多いともいえません。また、上位職の女性教員を増やすにはまず下位職として採用することが必要ですが、そもそも分野によっては女子学生が極めて少ない場合もあります。学生の段階で女性が少なく、進学段階でさらに減り、そこから大学教員となるとまたさらに減るとなれば、上位職どころか下位職の女性研究者比率を上げることも極めて難しいです。長期的な視点で考えなければどうにもならない現実があります。
また、意識を変えていくことの難しさもあります。出産後、基本的に17時には帰宅することを勝手に決めました。その時間には上がらないと子を寝かせる時間がどんどん遅れていくため、逆算して設定した時間です。でもこの背景にある状況は、産前にはあまり理解できていませんでした。職員の方には勤務時間という概念があるから会議は17時には終わるようにしたほうが良い、というくらいの意識だったので、子育て中の教員の家庭の問題に対して意識が甘かったなと反省しています。そして、自分が「子育て中の教員」にならなかったらどこまで理解できていたのだろうかと思うのです。そこまでの想像力があっただろうかと。自分にとって当たり前の働き方や時間感覚を変える必要性を認識するというのは、決して容易ではないと自分の経験からも感じます。だからこそ、どうやって意識や感覚をずらしていってもらえばよいのかの難しさを実感しています。道のりは長い。
自分にできることは限られているとしても、「女性だから」「男性だから」という語りがもう少し減るといいなと思いながら、できることからしていきたいと思います。息子が生きるこれからの世界が、性によって何かが妨げられない、全くないというのは難しいとしても今よりは少ない世界になっていることを願い、それより前の世代を生きる者としてできることにひとつずつ取り組んでいきたいと思います。