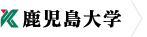専任教員ブログ
個人的に感じている学生の変化
伊藤です。
学期末です。それはつまり、レポート採点業務に従事する時期ということです。今回から成績提出がシステムで可能になりました。これまでマークシートに鉛筆で書き込んでいましたが、約550個の黒丸作成をせずに済んだことに感謝したいものです。
さて、そんな時期になると、学生調査結果などでは出てこないような学生の変化を感じることがあります。もしかしたら私だけがそう思っているのかもしれないけれど、そこそこ学生に関心を持って向き合っている教員であれば「あー、そうだよね!」「わかるわかる!」と言ってもらえるんじゃなかろうかと思うような、そんな変化です。
ちょうど今日手元に届いた『IDE現代の高等教育』No.673は「学生の変化をどう活かすか」だったので、様々な学生に関するデータも目にすることができました。納得できることが多々ありました。ただ、これから私が書くのはそういう性質のものではありません。
例えば、単位を取らんがために喰らいついてくる学生が以前と比べると減った気がする、とかいった、そんなレベルの話です。私は大抵の授業で毎回授業の振り返りレポートを課すのですが、それをとにかく提出しない学生というのが一定数必ずいます。成績評価に含めると初回授業で説明し、授業資料にも明記しているにもかかわらず、なぜか出さないのです。そういう出さない学生は以前からいたのですが、以前は成績評価ギリギリのタイミングで無理やりまとめて出してくる学生がそこそこいました。手書きで何枚もまとめて持参してみたりとかする学生も過去にはいました。そういう学生が減ったなあと感じています。
そういう学生が減ることそのものは構わないのですが、逆にちらほら表れているのが、そうした授業の振り返りレポート未提出が主な原因で不可となり、「何でですか?」と問い合わせてくる学生ですね。何でも何も、授業の振り返りレポートを出さな過ぎたからですよと言う以外にありません。一体何が疑問なのか、むしろこちらが疑問です。
以前と比べてということではなくよくわからないと感じているのは、同じ授業を何度も受けに来る学生ですね。一度落とした授業を何故また受けに来る?そしてなぜまた落とす?1回目と2回目、同じ理由で落として3回目となると、もう意味不明です。必修科目であれば、単位を取らにと卒業できないのだからまだわかります。しかし、選択科目の場合、他の科目を受ければよいだけです。その前に、2回目の時点で行動を修正したらよいだけなのに、何故また同じことをするのか。
学生との年齢差が広がり、私が親世代になってきて、「この学生はこれから大丈夫なのか?」と感じることが増えました。必修科目を担当していると「これを落としたら留年か...」「この1科目2単位のために約50万余分にかけるのか...」ということもあるのですが、親の立場に立ってしまうと勘弁してほしいよな...と思います。学生が自分で学費すべてを賄っていれば、留年しようとどうであろうと自分の責任だから仕方がないねと言えます。頑張って支払いなさいね、です。しかし、我が国では親が学費を負担するほうが一般的なので、自分の責任といえる範囲からははみ出ると思うのです。
まさか親は、我が子が必修科目のレポート提出遅延で留年となる未来など予想していないでしょう。大学1年生の時点では、約50万円という金額の重みもまだわかっていないのかもしれません。大卒初任給の平均金額を考えれば、平日5日×1日8時間×2か月働いてようやく得られる金額です。うっかりで済まされる金額ではないことの重みを理解してほしいと思います。
レポート採点作業はまだまだ続きます。今期は選択科目で「学びの公平性」をキーワードにしたレポートを課してみました。こちらが思いつかないような視点が出てきて、読んでいて楽しいです。
授業時間中に少し触れたこともあり、学内アルバイトができるようにしてほしいという意見がちょこちょこ出てきています。スポットバイトの学内版ですよね。授業の空き時間に少しでも稼ぎたい、でも、学外に出ていく時間はない、学内であれば信頼も置ける、ということで、ニーズがあるのでしょうね。SA制度やTF制度を設けるのに働いた身としては若干複雑な気分もありますが、それくらい経済的な支えを求めている学生がいるということなのかと思うと、これまた全く別の意味で複雑な気分にもなるのです。