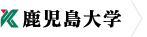専任教員ブログ
SKLV(South Kyushu Livestock Veterinary center)に行ってきました
伊藤です。
表題の通り、昨日は「遠足」に行ってきました。宮本先生、片平さま、大変お世話になりました。ありがとうございました。
SKLVは、南九州畜産獣医学拠点として曽於市の財部高校跡地に整備された施設です。地区産獣医学拠点ということで牛や馬、鶏がたくさんおり、その研修のために全国から獣医師を目指す学生さんたちが集っていますが、一般的な講義施設、さらには宿泊施設やレストランも整備されているため、獣医学に限らない研修の場としても利用可能です。
【SKLV(South Kyushu Livestock Veterinary center)】
https://sklv-soo.jp/
そこになぜお邪魔したかというと、まさしく獣医学に限らない施設利用への展開可能性を探るためです。先日読んだ、中村正史『東大生のジレンマ』の中で、都市で生まれ育って東大に入った学生さんが田舎で暮らしてみて、自分の視野の狭さを痛感したという話がありました。本学に来る学生さんの場合、東大生とは背景に違いがあるため、いわゆる都会で生まれ育った比率は低いでしょう。それでも、鹿児島市内で生まれ育ったとしても、「消滅自治体」「過疎地」といったワードをどこまで実感をもってイメージできるか、わかった気になって上から目線でものを言ってしまう恐れはないのか、という点が気になっていました。「地域活性化」「地域を元気にする」といったことに関心を持つ学生は、思いのほかいます。それでも、それがつまりどういうことなのかをどこまで理解しているのだろうという点に不安を覚えることも少なくありません。
「地域」とは=田舎ではありません。誰もがどこかの地域で生きているわけで、いわば生きるうえでの足場ともいえます。それが足場である以上、多かれ少なかれ誰もが地域と関わりを持つことになります。そこを元気にするというのはどういうことなのか、そもそも元気でないというのであれば、それはどういう状態なのか、といったことを考える必要もあるのではないかと思います。
そんな私の中にあるモヤモヤとした思いを考えるための拠点として、SKLVというのは素晴らしいところであり、ここを利用した取り組みを考えたいということで見学させていただき、お話を伺うに至ったわけです。
高等教育論という分野に足を突っ込みつつ、地方国立大学に奉職する身としては、大学の地域貢献ということについてもよく考えます。
地域で活躍する人材の育成ということも大学にかなり期待されているものの、教育プログラムを通じて地元就職率上昇を図るのは困難であるということは、当センターの中里先生の研究などでも明らかにされています。もちろん、「地域」を冠した学部を設置している国立大学もいくつもあり、そこで学んだ方々が各地で活躍されていると思います。それでも、大学にできるのは地域への関心を高めるところまでで、就職まで引っ張ることは難しいでしょう。
それと、「大学ならでは」の地域貢献という点について、もう少し考える必要があるのではないかとも思います。多分野複合的な知を持つ人の育成ももちろん重要ですが、特定の専門性を尖らせた人材もそれはそれで重要であり、どちらの方が、という話ではありません。それでも、専門家養成も大学が担っている役割のひとつであり、そうした一定の専門性を有した人材の育成と地域貢献との組み合わせも必要ではないでしょうか。SKLVはそうした観点からも非常に「面白い」と考えています。
SKLVをどう活用していくかについては、昨日お話させていただいていろいろ考えることができましたので、これから具体化させていきたいと思います。実働に繋げないと、せっかくお邪魔した甲斐がありません。まずはそこからです。