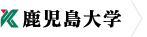専任教員ブログ
令和7年度新任教員FD研修会を開催しました
伊藤です。
標記の件について、昨日無事に終了しました。ご参加いただいた新任教員の皆さま、情報提供いただいた橋本先生、浅野先生、ありがとうございました。また、非常にお忙しい中、開会挨拶にお越しいただいた有倉先生、心より感謝申し上げます。
今回は、とにかく参加者が少ないというのが残念でした。昨年度も少なかったですが、それ以上でした。コロナ禍以前はこの時期でも20~30人は集まっていましたが、教員の行動パターンが変わったのか、忙しくてそれどころではなくなったのか。科研費申請書作成の時期なので、文書作成に追われていて精神的にそれどころじゃないのか。考えようと思えばいろいろと思い付きはするものの、どう考えても理由は1つではないですよね。来年度については、開催時期を授業期間中に移すか、新任教員に参加者を限定せずに前後期末に授業の振り返りをベースにした研修会を実施するか、ちょっと考えます。また、レクチャーの部分についてはオンデマンド化ですかね。そうすると、対面で行うのは座談会とかワークショップになってきますね。
そんなことを考えていると、授業と共通することに気が付きます。つまり、知識の伝達だけであればオンデマンドで問題なく、他者とのコミュニケーションを重視する部分こそ対面、という区分の仕方ですね。FDを大きな目的とした研修会の方法についても、改めて見直したほうが良いということでしょうか。
何かの企画を実施すると、それを機会としていろいろな気付きを得ます。今回得られた気付きとして重要なのは、まず上記の内容ですが、それ以外としては、「できる先生は何でもできるなあ」と再確認したことと、生成AI対応はどうしたものだろうということですね。前者については、常々思っていることですが、去年情報提供いただいたお2人もそうでしたが、ベストティーチャー賞を受賞されるような先生方は、決して教育能力だけが優れているわけではなく、教育も、研究も、管理運営業務もできるんですよね。どうするとそうなっていくのか、もともとの資質の問題なのか、それだけではなくキャリア形成のプロセスの問題なのか、明らかにできると良いのになと思いました。
生成AIの方は、11月開催予定のFD・SD合同フォーラムでも扱う話ですが、何とか対処しなければならないものの、こうすれば良いという具体的なものがあるわけでもない。しかも、急速に進化するため、「こうすればいい」「こうすべき」ということを考えたとしても、半年後や1年後には変わってしまう可能性大という、教育しきれない難しさも抱えています。それでも何もしないわけにはいきません。
学生に適切な利用をしてもらうにはどうしたらよいか。
不適切な利用をさせないためにはどうすればよいか。
不適切な利用が疑われる場面ではどうすればよいか。
考えても正解のない問いに大学としてどう向き合っていけばよいか。より良い授業を模索することとも共通する大きな課題に向き合わなければならない日々が続きます。