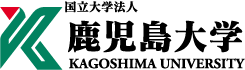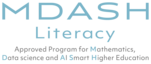平成30年度前期・後期「基礎教育入門科目」
1.自主学習時間を確保するための工夫や改善策
○宿題の難易度と量をやや増やす方向で課題の内容を検討している。
○単元が終了するたびにレポート(演習)課題を行う。採点をしてコメントを付けて返
却する。間違いの多かった問題の解説を行う。
○対応する章の予習(教科書を読んでくる)と復習(章末の演習問題を解く)を徹底さ
せる。
○二回に一度は小テストを行うようにして、復習が必要性を高める。
○統計学科目については、授業で取り上げた例や例題と類似する問いを復習の際に解い
てもらうようにし、授業の板書(追いつかない場合は写メも許可している)を整理し
て知識を身に付けてもらうように努力する。
○授業終了前に、説明した内容で特に重要な箇所を再度伝え、それに関連する練習問題
を次回の授業までの復習として課しています。
○自主学習時間を確保するため、章末問題(教科書の第1章~6章まで)を解くよう勧め
ている。同時に、第1章~6章の説明がそれぞれ終わるたびに解答例も配布し、自主
的に学習するよう促している。
2.授業改善に向けての試みや工夫
○授業内容と時間のバランスを微調整し、問題の解説を少し増やすことにした。例題を
解説した直後に、演習問題を解いてもらうことによって、問題のパターンとその解き
方を記憶させる。
○学生にこちらから送る「情報」を受け取ってもらうために、受け手となる学生に「受
信機」のスイッチを入れてもらう必要がある。このために、授業開始時に「面白いネ
タ」を用意して学生が聞く状態を整えて、授業を始める。
○物理学を面白くするには、科学の歴史や人物と関連付けて教えるのがよいと考えてい
る。できるだけ、物理学が包含する世界観や、法則の発見の経緯などを解説するよう
にしている。科学史に関連した書籍を、学生に読ませることができれば、なおよいと
思っている。
○授業のプリント配布を毎時間徹底する。こうすることで、次回授業で行われる小テス
トのための復習をしやすい環境をつくり、自習時間ゼロの学生を減らしていく。
○理論的なことに関する説明を充実させることが必要である。物理現象は、目では見る
ことができないことも少なくないことから、身近な例を示しながら、可能な限り水産
に関する例を挙げながら、説明できるように工夫していきたいと思っています。
○章末問題(教科書の第1章~6章まで)を解くよう勧めている。ただし、章末問題を解
くことを義務化するかは今後の検討課題としている。
3.授業改善についての意見、提案、要望等
○公開授業とすることを検討し、グループ討議に社会人も加わることにより、各学生に
刺激を与えるとともに、視野を広げることを目指す。
○公開授業として、社会人も加わることにより、緊張感をもって授業に臨んでもらう。