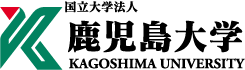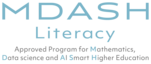平成30年度前期・後期「初年次セミナーⅠ・Ⅱ」
1.自主学習時間を確保するための工夫や改善策
○提出した課題に対して可能な限り丁寧にコメントは返すようにしたい。また、特に小
テストを課す授業においては、復習がしやすいよう授業で用いたスライドはmanabaに
掲載しておく。
○事前学習と事後学習については、授業前日までにmanabaで提出させるようにする。
○他の授業と比べ、自主学習時間は圧倒的に長い。毎回宿題を出しているためだと思わ
れる。ただし、テキスト通りに宿題を出すと、受講生のゴールとはかけ離れた学習を
多くさせることになるため、宿題内容を適宜変更するようにしていた。
○宿題は適宜変更し、宿題をこなすことが最終レポートの準備となるようにした。
○manabaで関連資料を受講生と共有する。
○図書館や自習室の利用を勧める。
○課題の改善:ある程度、長時間の作業を要する課題を増やす。もしくは、そもそもの授
業全体の設計を変える必要がある。
○予習復習不十分学生への指摘、また不十分さがすぐにわかるような課題設定が必要か。
2.授業改善に向けての試みや工夫
○授業の内容やレベル自体は他の初年次セミナーと合わせる必要があるので、新しい教
科書やマニュアルに沿ってシッカリ授業を進める事に努める。
○初年次セミナーにおいては、抽象的な内容にならないように、実例を示すべく教材を
集めるようにしています。
○グループ活動の意義をより積極的に感じられるような指示の出し方が必要だと考えて
いる。特に「初年次セミナー」など必修科目は根本的にモチベーションが低い学生も
いるため、何を目的として話をすればいいのかをなるべく説明し、話し合いの到達点
を示すようにしたい。
○授業中の活動成果をmanabaで提出させることで、学習活動に確実に取り組ませるよう
にする。
○論文やレポートの書き方など、方法を説明することが多く応用的に理解することが難
しいと思う。より想像が具体化できるように、事例を示しながらの授業を検討している。
○毎授業の初めに、その回の学習目標を提示したことから、「目的が理解できた」「授業
への導入がわかりやすかった」といった意見があった。
○グループ活動に対して好評であり、また学習効果も高まったと思われる。
教育効果を上げる為には、学習に対する動機付け(何故これらを学ぶことが重要なの
か)、授業内容に洗練(冗長にならない)、計画的かつ系統的な課題の提示、他人との
意見・情報交換が重要だと思われる。
○「専門用語が多すぎる」→教科書に明示された専門用語はそれほど多くないので、担
当教員の説明の中で知らず知らずに普段受講生が聞きなれない用語を入れて説明して
しまったのかもしれない。
○「レポート課題の内容がかぶっていたり、必要ない様な質問がある様に思える」→最
終レポートを完成させる為に取り組む課題と、単なるエキササイズとして取り組む課
題とが並在し、これらが不満の種になっていると思われる。後者は講義中で取り組ん
で前者に集中させた方が良かったと思われる。
○manabaとresponのさらなる活用を目指す。受講生に楽しいと思ってもらえる授業を
する。
○初年次セミナーは、講義・グループワーク(4-5名)、ペアワーク(2名)を組み合わ
せて、TPOを踏まえた教授法を毎回取り入れている。また、スケジュール進行表をス
ライドに投影し、授業の予定を最初に理解してもらうよう心がけている。
○授業マニュアルに必要以上に固執せず、出来るだけ要点を絞って特に大事な点を学生
に伝えるようにしています。
○様々な学習が以後の大学生活で重要になることの説明に力を入れたい。
○質問事項を授業の最後に書かせ、その日のうちに回答をmanabaにアップロードする方
法は、学生には評判が良いため更に改善の上、継続する。質問の回答を次の授業で取
り上げると、20分~30分もロスするため、質問は精査の上で、絞って授業中には回答
することにした。残りはmanaba上で読むように伝えることにした。
3.授業改善についての意見、提案、要望等
○論文やレポートが初めての学生のため、お手本となる論文を多く読む事が大切かと思
う。その際の読みのポイントについて指導を行うとさらに解釈しやすいのではないか。
○学部混成だとしても、自分が興味のあるテーマを選び、そのクラスには、そのテーマ
に合った教員を配置するというやり方もあるように思う。そうでなければ「グループ
で議論をしよう」と言っても、最終課題がそもそも個人で書くレポートなので、グル
ープで議論をするモチベーションも余地もない。また、内容の厚み、および、1年生
の前期に、プレゼンとレポート執筆の両方を身につける方が効率的に思われるため、
前期のみに、内容を統合し、教員のリソースも集中した方が良いと思われる。