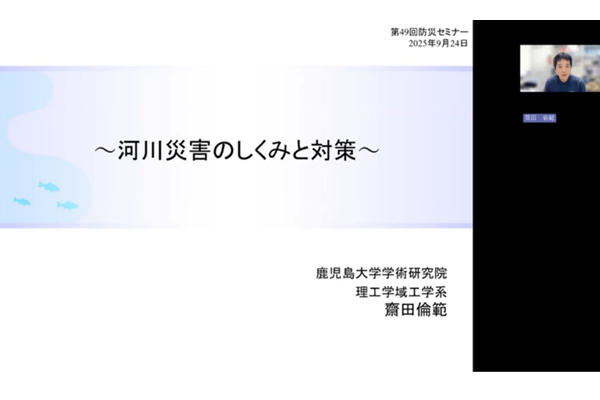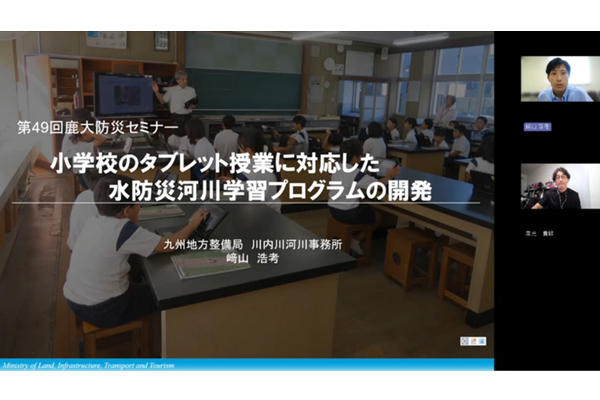【防災C】第49回鹿大防災セミナー「河川災害のしくみと防災教育」を開催
[記事掲載日:25.10.14]
9月24日、鹿児島大学地域防災教育研究センター主催の第49回鹿大防災セミナー「河川災害のしくみと防災教育」がオンライン形式で開催され、541名が参加しました。
本センター防災教育部門長の松成裕子教授(医歯学域医学系)の司会のもと、二つの講演が行われました。
はじめに、本センター運営委員の齋田倫範准教授(理工学域工学系)が「河川災害のしくみと対策」と題して講演を行いました。齋田准教授は、洪水のリスクが高い沖積平野に多くの人が暮らす日本の地理的特徴を指摘し、地盤の水分量が多いと土砂災害だけでなく河川の氾濫リスクも高まることを説明しました。また、越水や破堤により住宅地へ河川水が流れ込む「外水氾濫」について、映像を交えてその危険性を紹介。堤防を高くするだけでは被害が拡大する可能性があることや、避難は早めの判断が重要であることを強調しました。
続いて、本センター地域連携部門長の黒光貴峰教授(法文教育学域教育学系)が、九州地方整備局川内川河川事務所の﨑山浩考氏をゲストに迎え、「小学校のタブレット授業に対応した水防災河川学習プログラムの開発」と題して講演を行いました。黒光教授は、教育現場の負担を増やさず、継続的に実施できる防災教育を目指していると述べ、自然災害の恐ろしさだけでなく自然の恵みを感じる学びの重要性を紹介しました。
﨑山氏からは、平成18年の川内川出水を契機に、地域の防災力向上を目的として平成25年度に作成された「川内川水防災河川学習プログラム」について説明がありました。令和5年度からはGIGAスクール構想に合わせてICTを活用した教材を開発し、今年度より薩摩川内市の小学校で展開していることが紹介されました。
今回のセミナーでは、河川災害への理解を深めるとともに、防災教育の新たな可能性を考える貴重な機会となりました。参加者からは、「実践的で非常にわかりやすかった」「教育現場での活用を進めたい」などの声が寄せられ、今後の地域防災力向上への期待が高まりました。