トップページトピックス【防災C】レジリエント社会・地域共創シンポジウム「火山大噴火と地震に備える~災害を知り、地域防災力を高める~」を開催
【防災C】レジリエント社会・地域共創シンポジウム「火山大噴火と地震に備える~災害を知り、地域防災力を高める~」を開催
[記事掲載日:24.12.13]
12月7日、鹿児島大学地域防災教育研究センター主催、一般社団法人国立大学協会と鹿児島地方気象台共催による、令和6年度レジリエント社会・地域共創シンポジウム「火山大噴火と地震に備える~災害を知り、地域防災力を高める~」が会場とオンラインで開催され、地域住民、自治体関係者、学生など約300名が参加しました。
会場ロビーには桜島の大正噴火時の写真をAIカラー化した展示や、噴火による降灰をVR体験できるコーナーが設けられ、多くの来場者が見学しました。
開会にあたり、佐野学長の挨拶に続き、国立大学協会の位田専務理事から来賓挨拶がありました。
第一部では、酒匂センター長がセンターの取組や、大規模火山噴火に備えた調査研究を紹介し、シンポジウムの趣旨が説明されました。次に、井村准教授(総合教育機構共通教育センター)が「鹿児島県内火山の現状と備え」と題し、桜島の噴火歴史や火山についての理解と教育の重要性を強調しました。続いて、小林准教授(理工学域理学系)が「県内で想定される地震と備え」と題し、鹿児島県周辺で発生した地震や津波の事例を紹介し、予測の難しさと事前の備えの重要性について説明しました。最後に、鹿児島地方気象台の安藤地震津波火山防災情報調整官が「気象庁の地震・火山防災情報」と題し、気象庁が提供する防災情報とその活用方法を解説しました。
第二部では、「地域防災力の向上」をテーマにパネルディスカッションが行われ、酒匂センター長がコーディネーターを務めました。参加者からの質問に対し、耐震化や防災対策の経済的負担、火山噴火や地震予測、津波避難、大規模噴火時の交通網への影響など、多岐にわたるテーマが議論されました。各講演者からは、地域防災力向上に向けた意見が述べられ、安藤地震津波火山防災情報調整官は鹿児島地方気象台として、住民や学生を対象としたワークショップなどを通じた地域貢献を今後も継続し、積極的に参加することで地域防災力の向上に活かしてほしいと呼びかけました。井村准教授は災害リスクに対する「覚悟」の重要性を強調し、小林准教授は効率的な耐震化の推進を呼びかけ、事前の備えの重要性を再確認しました。
閉会にあたり、岩井理事(企画・連携担当)が挨拶を行い、災害予測の難しさを踏まえ、住民一人一人が知識を深め、防災意識を高めることの重要性が強調されました。
今回のシンポジウムでは、参加者から「実際の災害に対する備えを再認識できた」「今後もセンター主催の防災イベントに積極的に参加したい」といった感想が多く寄せられ、地域防災活動への関心が高まるとともに、今後の地域防災力向上に貢献することが期待されています。


(佐野学長の挨拶) (国立大学協会 位田専務理事の挨拶)


(VR体験の様子) (展示の様子)
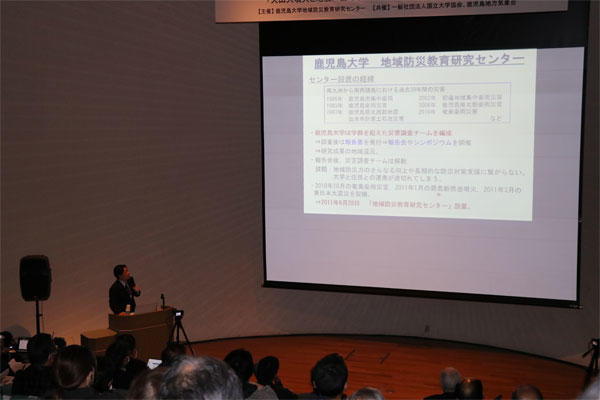

(酒匂センター長の講演の様子) (パネルディスカッションの様子)

(岩井理事の閉会挨拶)

