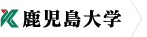センターの取り組み
シンポジウムの開催
大学入試改革シンポジウムの実施
鹿児島大学アドミッションセンターでは中教審で示された学力の3要素を持つ多様な人材を受け入れるため、入試改革に向けた議論を進めています。その際に必要となるのが地域の高等学校と共通認識を持つことであると考え、2016(平成28)年より毎年、入試改革に関するシンポジウムを開催し、学内外より多くの参加をいただいています。
過年度開催実績
2018(平成30)年
鹿児島大学大学入試改革シンポジウム
─入試の大括り化と教育プログラムを考える─
日時:2018年6月2日(土) 13:30~16:20
会場:鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館
本シンポジウムでは、入試の大括り化とその中での教育プログラムのあり方を巡って、大学の先生方より取り組みについて情報提供をいただくとともに、高等学校の先生より進路指導の観点から入試の大括り化がどう捉えられるかを報告いただいた上で、参加者全体で意見交換を行った。
まず、開会の挨拶を兼ねて、本学の教育担当理事・副学長・アドミッションセンター長より、シンポジウム参加者に向けて、本学の改革の背景とその進行状況についての説明が行われた。次に各大学の先生方より、大括り入試の導入と併せて「レイトスペシャリゼーション」を見据えた教育カリキュラムの一体的改革を進めていることや、文系・理系の後期一括入試の実現に至るまでの学内での調整の過程と、その基盤となった教育改革の取り組みの軌跡などについて報告があった。最後に、鹿児島県立の高等学校の先生より、高校の進路指導の視点から大括り入試のメリットや留意すべき点が挙げられ、大括り入試という選択を前に、生徒・学生への情報提供はもちろん、その進路選択をより慎重にサポートすべき旨が述べられた。
講演後の質疑応答・総括討議では、大括り入試の中で受験生や入学してきた学生の進路希望とどのように向き合い、サポートしていくべきかについて、大学・高校双方の参加者から質問が相次いだ。こうした講師の先生方と参加者のやり取りを通して、大括り入試の中でこそ、よりきめ細やかな進路指導が高校の現場にも、そして大学の現場にも必要であることが共有された。
2017(平成29)年
第2回 多面的・総合的能力の育成と入試を考えるシンポジウム
─高大双方の教育の取り組み事例から─
会場:鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館
本シンポジウムでは、多面的・総合的な観点での入試の実施や、そうした能力の育成を目指す特色ある取り組みについて、大学、高等学校の先生方より情報提供をいただき、参加者全体で多面的・総合的能力の育成と入試について意見交換を行った。
まず、鹿児島大学の教育担当理事・副学長・アドミッションセンター長より、開会の挨拶として、鹿児島大学が教育改革に取り組む背景について改めて説明が行われた後、「総合教育機構」の設立をはじめとした、進行中の改革の動向について紹介が行われた。次に各大学の先生方より、共通テストの記述式問題の位置づけや「講義型試験」など各大学の特色ある入試の取り組みについて紹介が行われた。最後に、鹿児島県の高等学校の先生より、SSH指定校の認定へ向けた取り組みに関して、その背景と状況について報告が行われた。
講演後の質疑応答・総括討論では、多面的・総合的な能力の育成や、そうした能力を測る入試の導入へ向かっていく中での対応についての質問が参加者から相次ぎ、その関心の大きさが改めて明らかになった。また、閉会後も、講師の先生方と参加者との間で個別に意見交
換が行われた。
2016(平成28)年
多面的・総合的能力の育成と入試を考えるシンポジウム
─地域志向とグローバル、高大双方の教育の取り組み事例から─
日時:2016年10月15日(土) 13:30~16:10
会場:鹿児島大学郡元キャンパス稲盛会館
本シンポジウムでは、地域及び地球規模で多面的な能力の育成を実践している大学、高等学校の先生方より情報提供をいただき、参加者全体で多面的・総合的能力の育成と入試について意見交換を行った。
まず、鹿児島大学の教育担当理事・副学長・アドミッションセンター長より鹿児島大学の教育と入試改革の現状について「地域志向」と「グローバル」の双方の観点から情報発信が行われた。次に鹿児島県の高等学校の先生方より、離島での地域に根ざした人材育成の取り組みについてのお話や、SGH指定校での地域に根ざしつつ地球規模でものを考え行動する人材の育成への取り組みについて報告があった。最後に京都府の高等学校(国際バカロレア認定校)より、国際バカロレア教育に関して、その概要と「正解のない問い」に向き合い、理解を深めるTOK(Theory of Knowledge)の取り組みについて情報提供があった。
講演後の質疑応答・意見交換では、地域の教育や国際バカロレア教育に関する質問が会場の参加者から相次ぎ、また、シンポジウム閉会後も講師の先生方と参加者との間で積極的に意見交換が行われた。