ベストティーチャー(令和6年度)
鹿児島大学では、本学の教育実践に顕著な成果をあげたと認められた教員に対して、その功績を表彰し、本学教員の意欲向上と、大学教育の活性化を図ることを目的としたベストティーチャー賞制度を平成30年度から設けています。
このページでは、令和6年度に受賞した教員の授業に対する心がけや創意工夫を行っている点などについてのコメントを紹介します。
ベストティーチャー最優秀賞
-

- 河野 航平
- 法文学部
- コメントを見る
-
この度は、ベストティーチャー最優秀賞という栄えある賞を賜りまして、大変光栄に存じます。ご関係の先生方、職員の皆様に心より御礼申し上げます。
私が授業において最も大切にしていることは、受講者に対して誠実であることです。時間を守る、十分な情報提供を行う、不手際を真摯に詫びる、そのような当たり前のことを確実に行うよう心がけています。他方で、不当な要求に対して毅然とした態度で接することも、受講者全体との関係では、誠実さの意味するところの1つであると考えています。
受講者から評価していただいている取組みの1つとして、講義科目における休憩時間の導入があります。90分の講義中に1回か2回、3~5分の休憩時間を設けています。その間、私は一切話しません。こちらとしては、言葉どおり「休憩」のつもりであり、SNSを眺めるのでも、友人と談笑するのでも、緊張が解けるのであれば時間をどう使っても構わないと考えていました。ところが、余力のある一部の受講者は、この時間を活用して、ノートを整理する、講義ごとに課している正誤問題に取り組む、他の受講者と疑問点について話すなどしているようです。教員が何もしないことで、かえって受講者の能動的な学びを促すことになるという、予想外の学習効果がありました。なお、この取組みは、法文学部のFD活動(教員授業参観)を通じていただいたご助言を私なりに解釈し、反映したものです。法文学部の先生方には頭が上がりません。
以上の休憩時間を除けば、ほとんど全ての時間を講義に充てています。雑談等はしません。したがって、このような賞の候補になること自体、私にとっては意外なことでした。鹿児島大学の学生には、遊びのない講義を受けるだけの十分な準備があり、その意欲もある、ということでしょう。学生を侮り、教育の質を下げるようなことがあってはならないと、身が引き締まる思いです。今後も、学生の能力や意欲を過少評価することなく、真摯に教育の改善に向き合う所存です。
-

- 日髙 佑郁
- 共通教育センター
- コメントを見る
-
このたびは、ベストティーチャー最優秀賞に選出していただき、ありがとうございます。受賞にあたって、毎年授業改善アンケートにたくさんの有意義なコメントを寄せてくれる学生に感謝したいと思います。
「英語IB(Academic Writing)」は、1年生対象の共通教育の必修科目で、パラグラフやエッセイのライティングに重点を置きつつ、四技能を統合して学ぶ授業です。学生は、英語によるアカデミック・ライティングのプロセスやストラテジー、構成や語彙・表現を学ぶとともに、互いの文章へのピア・フィードバックにも取り組んでいます。
授業設計においては、ライティングの技術を伸ばすことは大前提ですが、何よりも学生が楽しく、安心して自分の考えや気持ちを表現できるような雰囲気づくりを重視しています。そのため、スピーキング活動を多く取り入れたり、学習コンテンツをチーム戦のゲーム形式にしたりするなど、初対面の学生同士が信頼関係を築いた上で学べるよう工夫しています。スライド資料については、色彩やレイアウトに配慮し、視覚的に情報を捉えやすいデザインを心がけており、説明内容の明瞭さや話すスピードにも配慮しながら、理解しやすい授業展開を目指しています。また、令和7年度からはAI技術を取り入れ、学習の個別最適化やフィードバックの質の向上を図っていますが、学生一人一人に教員が個別にフィードバックを行うことも大切にしています。
AIの進化により言語学習の形は日々大きく変化していますが、個人の経験に根ざした視点や、相手への思いやりを伴う、いのちの宿る言葉のやりとりは、テクノロジーでは再現することができません。言語とは本来、他者とつながるための手段です。だからこそ、教室という場で仲間と共に言語を学ぶことに、今も変わらず大きな意義があるのだと思います。これからも時代の変化に応じた工夫を重ねながら、鹿大生の学びを支える授業を目指して、授業改善に取り組みたいと思います。
ベストティーチャー賞
-

- 梅林 郁子
- 教育学部
- コメントを見る
-
この度は、令和6年度ベストティーチャー賞を賜り、誠にありがとうございました。また、積極的に授業に取り組まれた学生の皆さん、ならびに教育学部教育改善委員会の先生方をはじめ、お力添えをいただきましたご関係の諸先生方・職員の皆様に、重ねて心より御礼申し上げます。
私は音楽科の教員で、専門は音楽学(音楽の研究)ですので、ふだんの授業では主に音楽科の学生を対象に、「学問としての音楽」に関する科目を担当しています。そのため、今回の評価も、令和6年度に担当した「民族音楽学概論」(前期・選択)および「音楽史A」(後期・中等必修)における、学生の皆さんによる授業アンケートの結果がもととなっています。「民族音楽概論」は世界各地の音楽を、「音楽史A」は西洋における中世から現代までの音楽を扱っており、いずれも内容が多岐にわたる講義です。そのため、学生の皆さんにとって理解しやすい授業になるよう、毎回試行錯誤を重ねています。そこで、以下に私が授業づくりで心がけている点をいくつかご紹介させていただきます。
前回の復習:どれほど一生懸命学んでも、前回から1週間も経過すると学習内容が記憶から薄れてしまいます。そこで、授業の冒頭に重要事項を振り返る時間を設け、キーワードや要点を全員で確認することで、授業へのウォーミングアップとしています。
授業の展開:授業は基本的に講義形式ですが、音楽の授業では学んだ知識が実技や作品理解に結びつくことも重要です。そのため、パワーポイントに加え、楽譜や歌詞などの資料、音源や映像を数多く準備し、学んだ内容が実際の作品や演奏にどのように活かされているかを確認できるようにしています。また、準備できる民族楽器については、学生に実際に音を出してもらい、奏法や音色を体感できるようにしています。さらに、重要事項については授業中に繰り返し質問をしたり、取り上げたりして、知識の定着を図ります。
授業のまとめ:授業の最後には確認問題を実施しています。まずは個人で取り組み、その後、周囲の学生と協力して解答していきます。これらの問題は、教員採用試験の予想問題・過去問題をもとに作成しており、学んだ内容を実際の試験に応用できるよう工夫しています。
学生の皆さんからのアンケートでは、以下のコメントをいただきました。
・授業終わりの確認テストや授業最初に前回授業の復習があり、学習内容を定着させるようにしていた所がよかった。
・映像や音源などをたくさん聴くことが出来たので、楽しんで講義に参加することが出来た。また、内容もとても理解しやすかった。
・教採の対策もしてくださって、とてもためになりました。また、普段は、見れないような楽器を持ってきてくださっていて、とても興味深かったです。
一方で、アンケート結果を見る限り、中等必修科目である「音楽史A」では、「主体性」や「理解度」の項目において、なお改善の余地があると感じています。広範な知識を網羅しつつ、学生がより主体的に授業に参加できるよう、今後も授業内容や進め方を見直し、さらなる改善に努めてまいります。
-
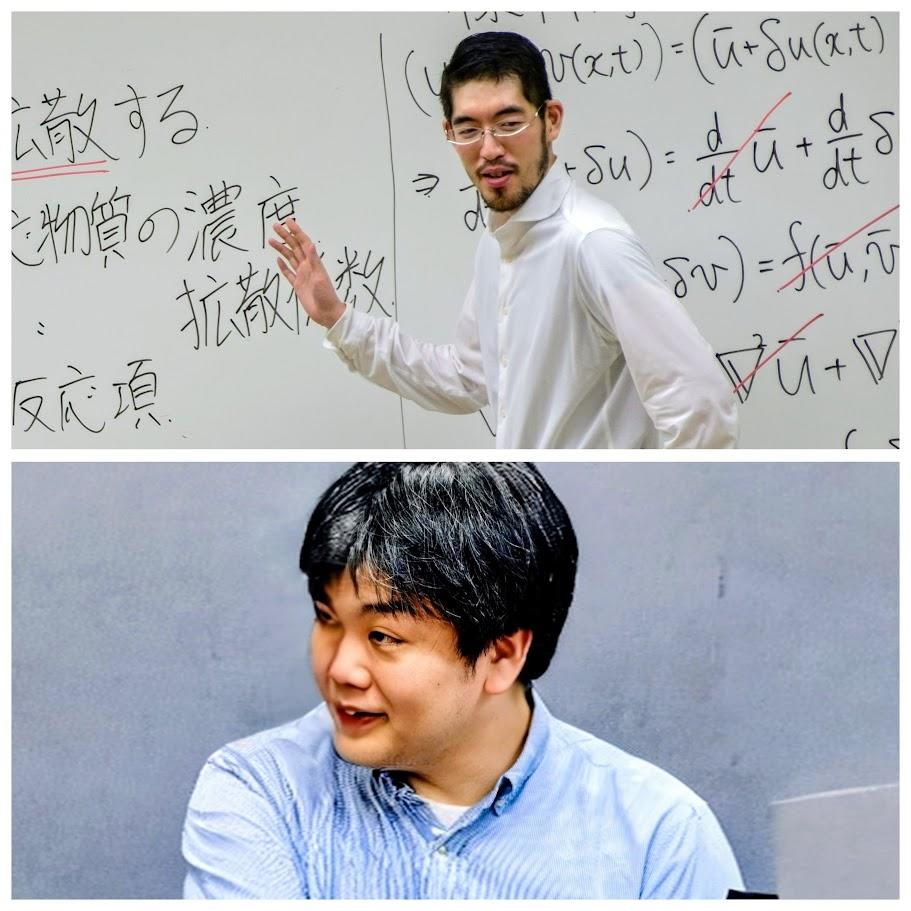
- 理学部(秦 重史,三井 好古)
- 理学部
- コメントを見る
-
令和6年度鹿児島大学ベストティーチャー賞に選出していただき、誠にありがとうございます。
今回選出いただいた、「ファインマンの力学」(秦担当)と「物質科学入門」(三井担当)は、1年生向けの共通科目として開講すると同時に、高大接続科目(先取り履修科目)として高校2・3年生も受講可能な科目です。
大学生の受講者にとっては理学科共通科目として自分の所属するプログラムや他プログラムの様々な分野を学べるように、高校生の受講者にとっては大学生向けの高度な内容を理解できるようにそれぞれの授業内容を工夫しています。ファインマンの力学ではコンピュータシミュレーションを通して、学生が実際の理論物理学研究を体験する機会を提供することで、学生の意欲向上を図っています。物質科学入門では、社会で用いられている物質に対する文献調査を受講生が自ら行い発表することで、講義内容の理解を深めることを目指しています。
昨年度まで高大接続科目をコーディネートしていただいた中西裕之先生(現・石川県立大学), 理学部開講の先取り履修科目8科目を担当いただいている先生方および受け入れ手続き等ご担当いただいております事務職員の皆様に厚く御礼申し上げます。
今後とも、理学科学生の教育と高大接続教育の充実のため、さらなる授業改善につとめてまいります。
-

- 永野 聡
- 医学部保健学科
- コメントを見る
-
この度、ベストティーチャー賞を頂くことになり、関係者の皆さま、そして評価してくれた学生さんに感謝申し上げます。
私は5年前に医学科から保健学科に異動して来ました。保健学科は、看護、理学療法、作業療法と異なる専門職を目指す学生が同じ講義室で学ぶことも多く、到達目標や深達度の違いに配慮しています。講義では、まず初めに講義内容に関連した国家試験の問題を数問提示します。この時点で解説はしないので、ほとんどの学生は答えがわからない(おそらくやや不安な)状態で講義を聞き始めることになります。講義を進めながら、その問題の解説もしていきます。講義の最後には小テストを行い、学生の理解度をチェックしています。「一つの講演のなかで3回同じこと言うと聴衆の心に残る」と教えられたことがあり、大事なポイントを講義の初め、講義のなか、最後の小テストと3回強調すれば学生の心に残ると信じて続けています。
大学院の講義では、社会人として働きながら学ぶ学生が多く、学部との違いを出すように気を付けています。学部卒業後、臨床業務に従事するとさらに高度・実務的な知識の必要性を自覚すると思います。大学院講義では、例えば薬理学では実際の薬剤の使い方や副作用、病態生理学では診療ガイドラインの解説や最新の研究など、より実地的な内容を提供しています。特に理学療法士の学生から評判が良いのが、手術手技の説明や手術動画の視聴・解説です。手術室でどのような治療が行われたのかをしっかり理解したうえでリハビリをすることは患者さん、理学療法士双方にメリットがあると思います。
今回の受賞で私の取り組みが間違っていなかったと感じました。今後も、医療系専門職それぞれの学生が臨床に出た時に、学んでおいて良かったと思ってもらえるような講義を提供していきたいと思います。
-

- 三橋 廷央
- 水産学部
- コメントを見る
-
令和6年度鹿児島大学ベストティーチャー賞に選出いただき、誠にありがとうございます。推薦にあたりご尽力いただいた学部FD委員の皆さま、何より私の授業を高評価してくれた学生の皆さんにお礼と感謝申し上げます。そしてお忙しいところ選考いただいた井戸学長をはじめ、理事の皆さまに心から深く感謝申し上げます。
私は、附属練習船かごしま丸の航海士/教員を経て、令和5年度に陸上教員に転じ、主に学部の海技士養成プログラム科目の講義と演習及びプログラム登録学生(定員11人/学年)の資格試験と進学・就職支援を担当しています。私自身は、まだきちんとした授業を行えているとは考えておらず、附属練習船の教員や海技士教育を行っている他大学の教員と情報交換しつつ、常に試行錯誤を重ねている状況です。
海技士とは大型船舶に船長・航海士等として乗務するために必要な国家資格です。水産学部は、東京海洋大学海洋科学専攻科(登録船舶職員養成施設)と連携して、外航船航海士のエントリー資格と言える三級海技士(航海)の資格取得を目的とした教育を行っています。海技士養成プログラム(登録定員 11名/学年)の授業では、関係法令に定められた養成施設の教育内容を網羅しつつ、プログラム登録外の受講学生にも興味を持って受講してもらえるように講義内容のバランスを配慮しています。
今回の授賞対象となった「基礎測位学」は、2年生前期に開講される授業で、主な航法と洋上での船位決定(GPS測位を含む)について解説し、その基礎となる地球の形状や緯度・経度(測地系)まで含めて講義しています。授業では、海里(マイル)、緯度・経度における60進法など、普段は縁のない単位や計算も多いため、図や写真、動画などの素材が豊富な丁寧なスライド(レジュメ)の準備を心掛けています。今回、学生の皆さんから、そうした授業資料の見やすさ・分かりやすさを評価して頂けたとすれば、素直にうれしく感じます。また、学生がGPS機能を持つスマートフォンを保有しているので、ミニッツペーパーでは、地図アプリを活用する課題に取り組んでもらい、GPS測位等の授業内容を身近に感じて学びを深めてもらうきっかけ(仕掛け)作りになればと考えています。毎回の講義の最後には、respon/manabaを活用して、その回の講義内容の理解度自己評価や講義内容に対する質問・コメントを寄せてもらい、次回講義の冒頭でそれらの質問等を全員で共有しつつ回答しています。学生の質問やコメントに私の方が気づかされることも多く、こうしたフィードバックを通して、継続的に授業の内容見直しや双方向性を高めていきたいと考えています。
冒頭で述べた通り、改善すべき点は数多くあります。より充実した教育を提供できるように、今後も自己研鑽に努めてまいりたいと思います。