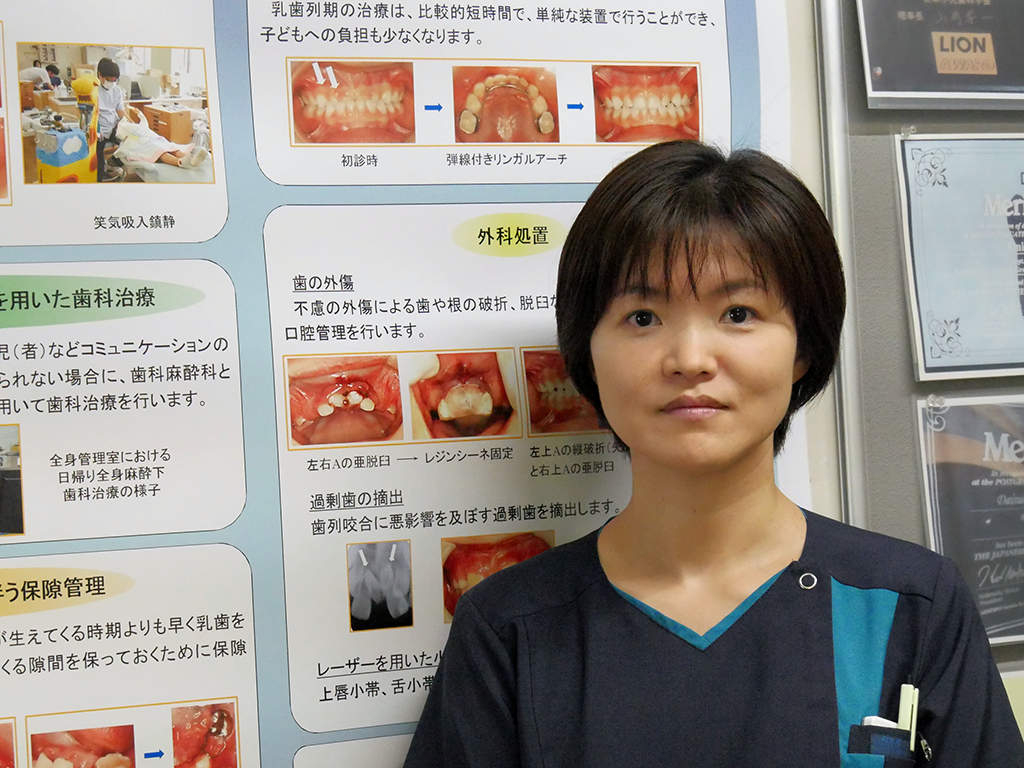子どもの口唇閉鎖不全(お口ぽかん)の有病率を明らかに

子どものお口ぽかん(専門用語で「口唇閉鎖不全」と言います)は、口唇を閉じる力である口唇閉鎖力の発達と関係があります。口唇閉鎖力が弱くなると、口の中が乾燥してう蝕や歯周疾患などに罹患しやすくなったり、歯を取り囲んでいる口唇・頬と舌の力のバランスが崩れて歯並びやかみ合わせが崩れてしまうことがあります。また、全身への弊害も示唆されていることから、早期からの積極的な対応が必要です。
小児期の口腔機能(*1)は常に新規の獲得とその積み重ねによる発達の過程にあるため、各成長のステージにおける口唇閉鎖不全の特性について理解し、患児の機能を評価する必要があります。そこで当科では、新潟大学小児歯科、広島大学小児歯科、大垣女子短期大学との共同研究で、未就学・学童期の小児における口唇閉鎖不全の特性ならびに、口唇閉鎖不全が未就学児の顔貌形態に与える影響について明らかにしてきました。
小児の口唇閉鎖不全に関する疫学調査を行った結果、口唇閉鎖不全が疑われる小児は全体の30.7%で、増齢的に増加傾向があること、また、顎顔面領域(*2)の形態だけではなく、口呼吸(*3)やアレルギー性鼻炎などとも関連していることが示唆されました。
口唇閉鎖不全が未就学児の顔貌形態に及ぼす影響は?いつから?

さらに、口唇閉鎖不全が小児の顔貌形態に及ぼす影響について調べました。鹿児島県内の3~5歳の未就学児444名を対象として、顔面の表面形態を非接触型3次元形態計測機(*4)を使ってスキャンしました。日中お口が開いている小児を「口唇閉鎖不全群」とそうでない小児を「口唇閉鎖群」として分類し、両群の顔貌形態について比較検討しました。
その結果、口唇閉鎖不全群の方が鼻が低い、口元が突出している、顎が後方に下がっているといった特徴が明確になりました。また、これらの形態的特徴は、3歳の時点ですでに出現することも判りました。以上の結果からも、小児の口唇閉鎖不全は早期に改善するべき状態だと考えられます。
口唇閉鎖不全を早期に発見し、早期に改善することは、将来起こり得る歯科的ならびに全身的弊害を未然に防ぐ有効な手段となる可能性があります。歯科医院では、お口ぽかんの子どもに対して口唇閉鎖力を向上させるための各種訓練を行っていますが、現在当科では、どのような訓練がどのくらいの期間で効果が出てくるかについて検証を行っています。
用語解説
(*1)口腔機能とは、食べる(噛む、味わう、飲み込むなど)、話す(発音、会話、歌うなど)、呼吸をするといった機能のこと
(*2)上下の歯と口を含めた顎全体のこと
(*3)鼻を使わず口から息を吸ったり吐いたりすること
(*4)レーザーや光を用いて立体物の3次元座標を読み取り、3Dデータを構築する機器