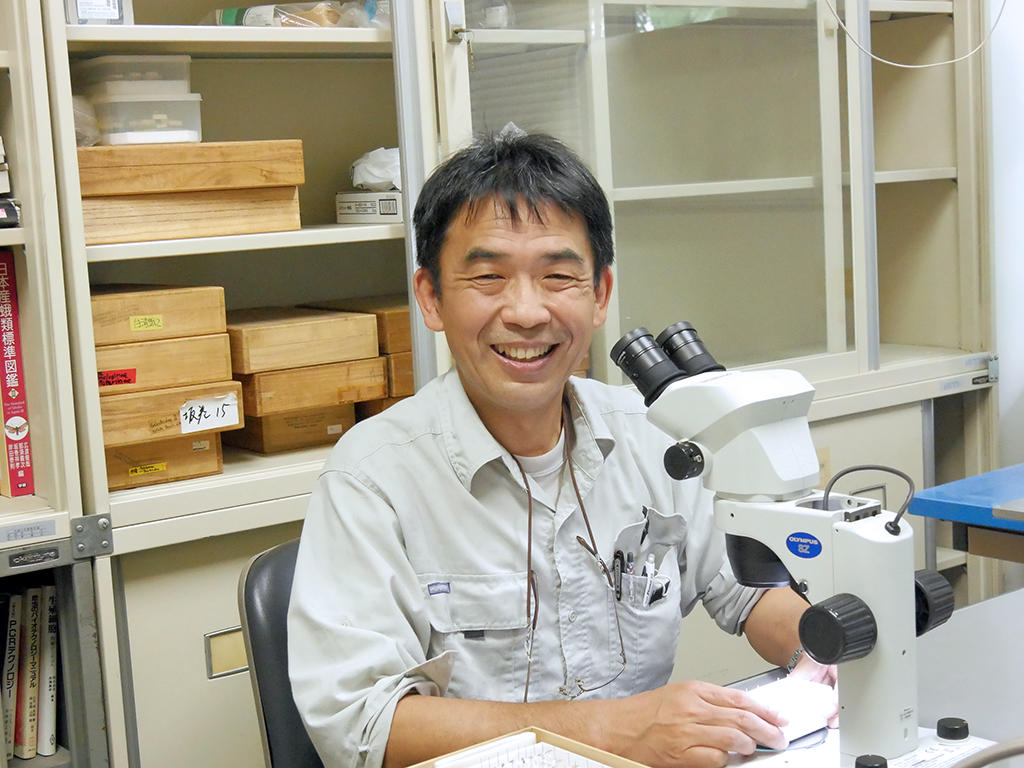昆虫研究の基礎:名もない虫たちを分類する

日本では今でも毎年100種以上の新種・新記録昆虫が見つかっています。特に、世界自然遺産の島々を含む南西諸島では、全く人目に触れることすらない昆虫たちがまだまだ多数生息しています。
私たちの研究室では、南西諸島や南九州の昆虫相を解明するため、形態学、形態測定学、分子生物学的なテクニックを使用して新種記載*1や新記録種の発表、分類体系の再検討などの研究を行っています。2020-21年には瑠璃色の金属光沢をもつ体長12-13㎜程の「ルリゴキブリ属*2」の3新種を記載しました。この属のゴキブリは従来八重山諸島に1種存在することが知られていましたが、私たちのグループが2005年に八重山諸島から900キロも離れた宇治島という無人島で、未記載*3のルリゴキブリ属の1種を見つけ(写真1)、その後15年かけて、南西諸島各地から類似の未記載ルリゴキブリ属を発見し、世界中のこのグループのゴキブリの記録と比較した結果、これらの未記載ルリゴキブリ属がアカボシルリゴキブリ、ウスオビルリゴキブリ、ベニエリルリゴキブリの3新種に分かれることを解明し、発表に至ったのです。
この他、研究室では翅を広げても1㎝に満たない小さな蛾などの新種記載・分類などにも力を入れています。
昆虫研究の応用:天敵や害虫の性質に合わせた防除法で化学農薬使用を低減

自然界には食うものと食われるものの関係が必ずあります。そのため、自然環境下では害虫や天敵*4の数も互いに極端に増えすぎることなく、バランスがとられていものです。このような現象によって、あたかも自然環境が害虫防除をする自律的な力を持っているように見えます。
私たちの研究室では、天敵による生物的防除法や害虫の性質を利用した物理的防除法*5を組み合わせることで、化学農薬の使用を抑制して、前述のように自然環境が持つ自律的な害虫防除の力を活かした害虫防除体系の確立を目指しています。日本の自然環境下にも害虫を捕食する肉食性の昆虫やダニが多数います。これらが露地圃場内でうまく働けるように、これらの捕食性天敵が好む花やその他の植物を混植した圃場環境作り、あるいは殺虫剤の代わりとなるが、天敵には悪影響のない物理的な防除法の研究をしています。
近年取り組んでいるのは50℃程度の低温水蒸気を茶園に散布して(写真2)、天敵を殺さずに、茶樹表面の害虫だけにダメージを与える方法の研究で、農業機械メーカーや飲料メーカー、鹿児島県の試験場などとタッグを組んで取り組んでいます。
用語解説
*1新種記載:新種の形態的特徴と分類学的位置および学名を示した論文が学術誌に認められ掲載されること。
*2ルリゴキブリ属:ゴキブリ目ムカシゴキブリ科の1属で体の背面に青緑色の金属光沢を持つ特徴のあるグループ。現在世界から23種知られており、そのうち4種が日本に生息する。
*3未記載:学名が付けられていない種。
*4天敵:害虫を捕食するか、あるい寄生して害虫を殺す生物。
*5物理的防除法:物理的な作用あるいはエネルギーなどを使用して害虫を防除する方法。殺虫剤で防除する「化学防除」や天敵で防除する「生物学的防除」に対する概念。