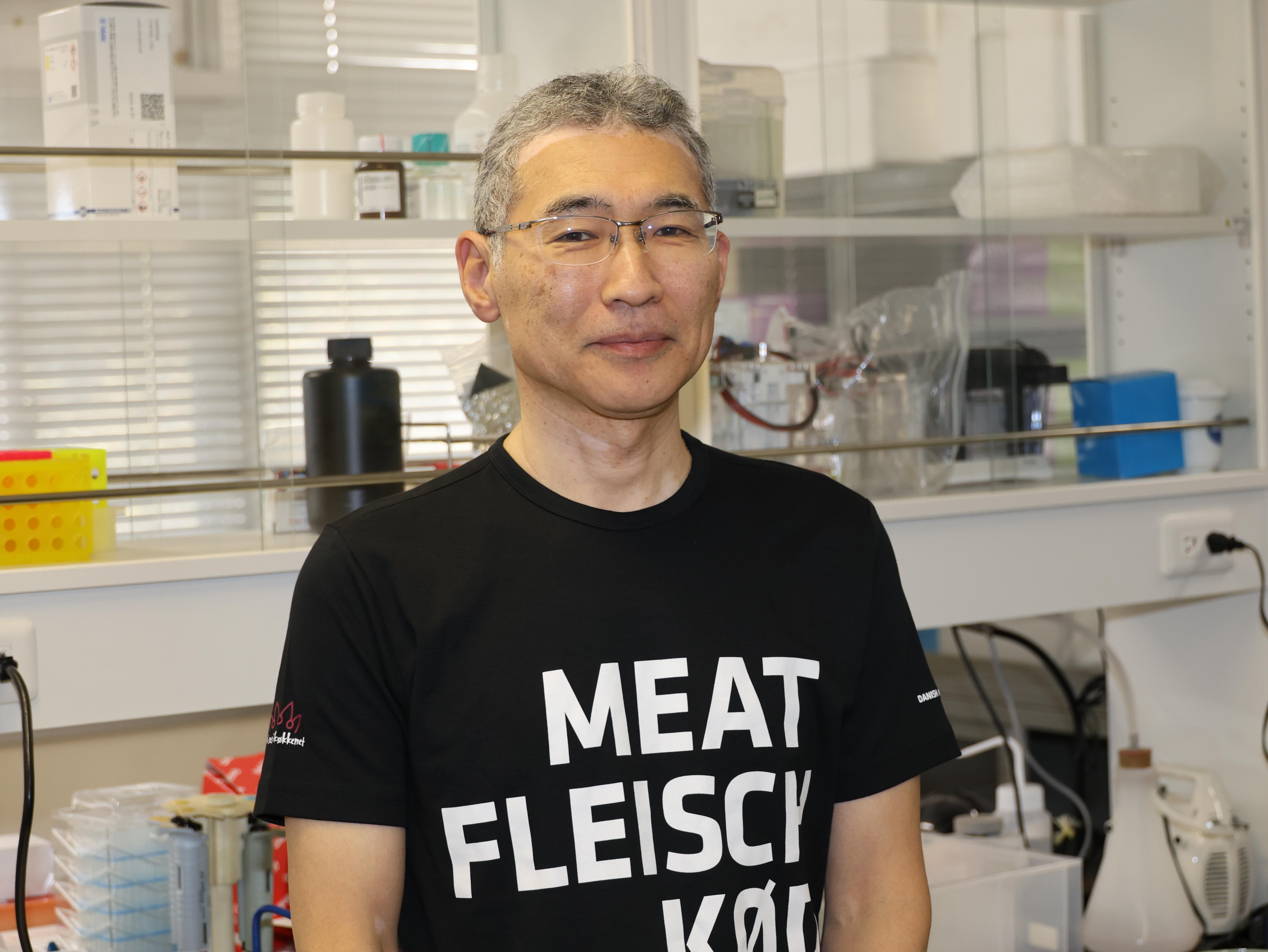食肉生産の上流から下流までの骨格筋または食肉を分子レベルで解剖

皆さんがお肉を食べるのは、どのような理由からでしょうか?食肉の味や香りは、畜種、動物が食べる餌と飼育環境、食肉管理や調理の条件によって違います。食べる側が感じる「おいしさ」にはさまざまな個人差がありますが、多様な食肉の存在は私たちの食生活を豊かなものにしています。そして、タンパク質やアミノ酸などの栄養素を豊富に含む食肉を適度に摂取することで皆さんの健全な体がつくられます。食肉はもともと家畜の骨格筋組織であり、動物個体の遺伝的背景、骨格筋の成長速度などの生理学的性質、多様な生体分子の構成だけでなく、家畜が食べた餌や育った環境、経験したストレス、また、食肉の保存管理条件も食肉の風味や栄養価に影響します。そして食肉、すなわち死後の骨格筋細胞では、生命活動停止により生時と異なる生化学反応が起こり、食肉へと変化を遂げます。私たちの研究室では、さまざまな背景をもつ家畜骨格筋や食肉をメタボロミクス(*1)やエピジェネティクス(*2)などで「解剖」し、分子レベルで食肉生産過程を解明しています。家畜生産を食肉からさかのぼって考えることで、家畜の筋肉、そして食肉が生体分子をもとにどのようにでき上っていくのか、家畜の飼養環境でどのように変わるのかを知ることができます。
肉用牛の環境適応メカニズムの解明で体質改変をめざす

近年、世界人口の急増、地域紛争、気候の温暖化、それによるエネルギーや食物、飼料原料の供給の不安定化、家畜と動物由来タンパク質に対する人々の意識の変化などの問題が浮き彫りになってきました。人類にとって必要なタンパク質を確保するために、培養細胞、昆虫、植物ベースのタンパク質食材が開発されつつありますが、従来の食肉をどの程度代替しうるのか、結論は出ていません。どうすれば国内でタンパク質を持続的に供給できるのか、その解決策が問われています。一方で私たちの研究室では関係機関と協力しながら、肉用牛の代謝およびエピジェネティクスが、栄養を中心とした環境ストレスに適応して変化する可能性を見出してきました。その研究成果をもとに肉用牛の体質を変えることで、より健全で効率的な肉用牛生産が可能と考え、その飼養技術の開発に取り組んでいます。肉用牛生産の基礎研究では、糖、脂質などのエネルギー代謝、アミノ酸などの栄養素代謝、内分泌などを細胞生物学や分子生物学の面で解明していきます。体の仕組みの理解は簡単ではありませんが、広がる世界は知れば知るほど生命の奇跡と謎に満ちていることに驚かされます。グローバルな課題を見据え、黒毛和種牛の生産中心である鹿児島で肉用牛の基盤研究に取り組み、「面白い」成果を世界に発信していきます。
用語解説
*1 代謝物(metabolite)の網羅的な解析。分析技術が進化を重ね、骨格筋では一度に200種以上の化合物検出が可能。
*2 DNA塩基配列によらない遺伝子発現制御の仕組み。DNAメチル化、ヒストンタンパク質の修飾、microRNAの分子機構の解明が進んでいる。