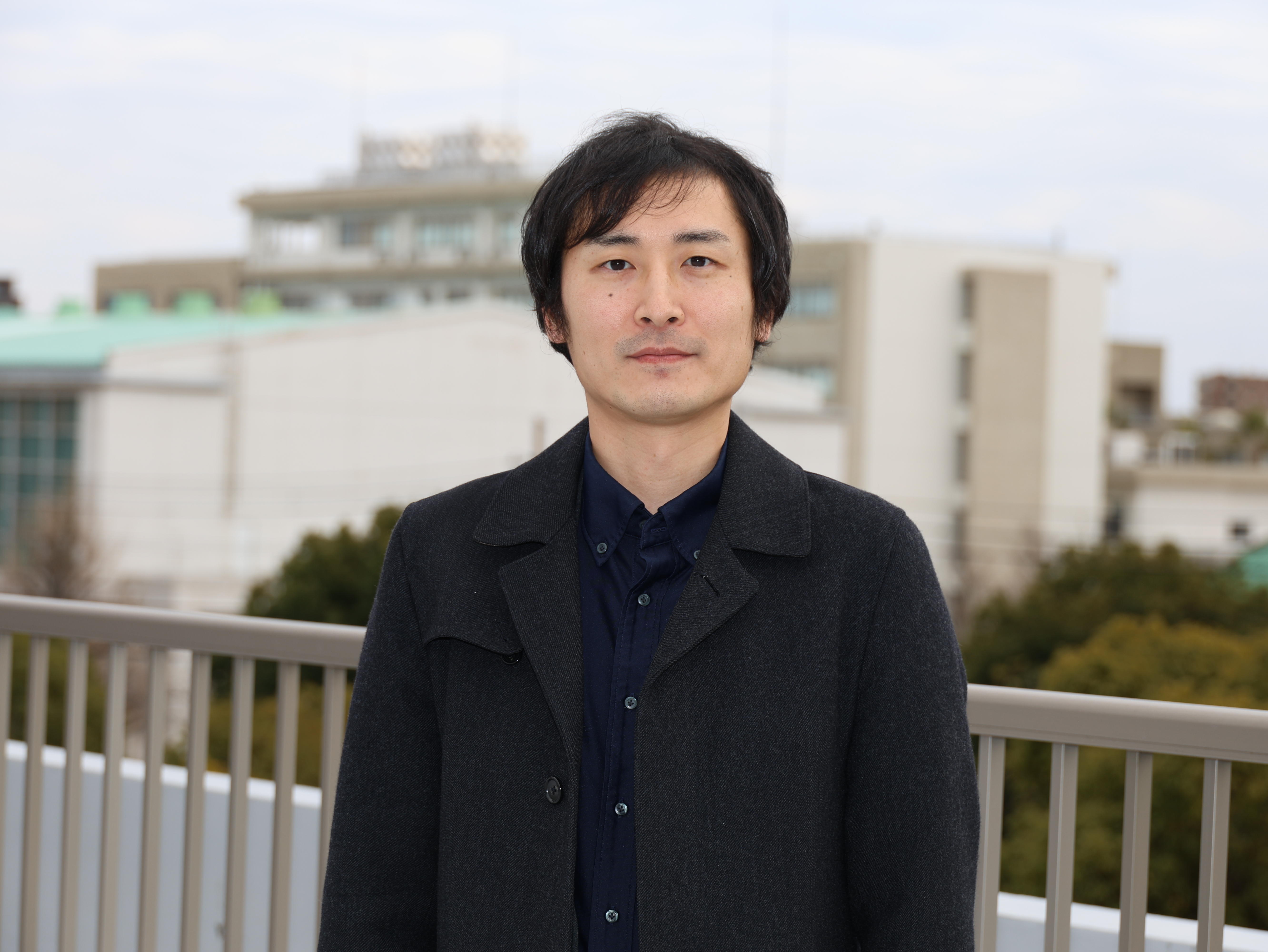非行・犯罪と関わる心理職

近年、心の専門家への社会的なニーズは高まっており、その活躍の場は多岐にわたります。主な領域として、教育、医療・保健、福祉、司法・矯正、労働・産業などが挙げられますが、その中で司法・矯正領域を主たる活動分野とする心理職は3〜4%程度と言われています。安全・安心な社会を作るための重要な役割を担っているものの、非行や犯罪などに関わる情報は秘匿性が高く、それゆえ、現場の実態も表に出ることが少ないです。このような実態の不透明さが、非行少年・受刑者や矯正施設等に対する世間の誤った認識や偏見を生むこともあります。また、法務省が行った調査では、矯正施設で働く職員の多くが、自らの仕事が一般の方に正しく知られていないということへの葛藤を抱えていることが明らかになっています。
私はかつて矯正施設の心理職だった者として、施設の中と外の架け橋となれたらと思い、研究に取り組んでいます。具体的には、司法・矯正領域で活動する心理職のやりがいや課題に関する研究や、少年院在院者に対するインタビューを通じた教育・支援の効果に関する研究などを行ってきました。
社会全体で再非行・再犯防止に取り組む

非行少年や受刑者等の更生は、簡単ではありません。当然、少年院や刑務所における教育で完結するものでもありません。
まず大前提として、非行や犯罪の事実を正確に把握するための「捜査」がなされ、捜査で得られた資料をもとにして、最適な判断を「司法」が行います。そして、「矯正」において、再非行・再犯を防ぐための教育・支援を施され、社会復帰後に安定した生活を送れるように「更生保護」による社会内処遇が行われます。一人の非行少年、受刑者等に対して、様々な機関や支援者が協働・連携しながら関わることが、再非行や再犯を防ぐためには不可欠と言えます。鹿児島県では、再犯防止推進会議を開催し、非行や犯罪をした人が再び罪を犯さないようにするために、関係各所と連携するための取り組みを行なっており、私も委員として参加させていただいています。
また、私個人としても少年鑑別所等の機関との繋がりを持たせていただき、私からは研究等の最新の知見を研修等で提供させていただき、逆に機関からは現場の実情を教えていただくという関係を築いています。大学院生の実習先としても受け入れていただき、次代を担う司法・矯正領域の心理職を育成するための教育活動の一部にもなっています。