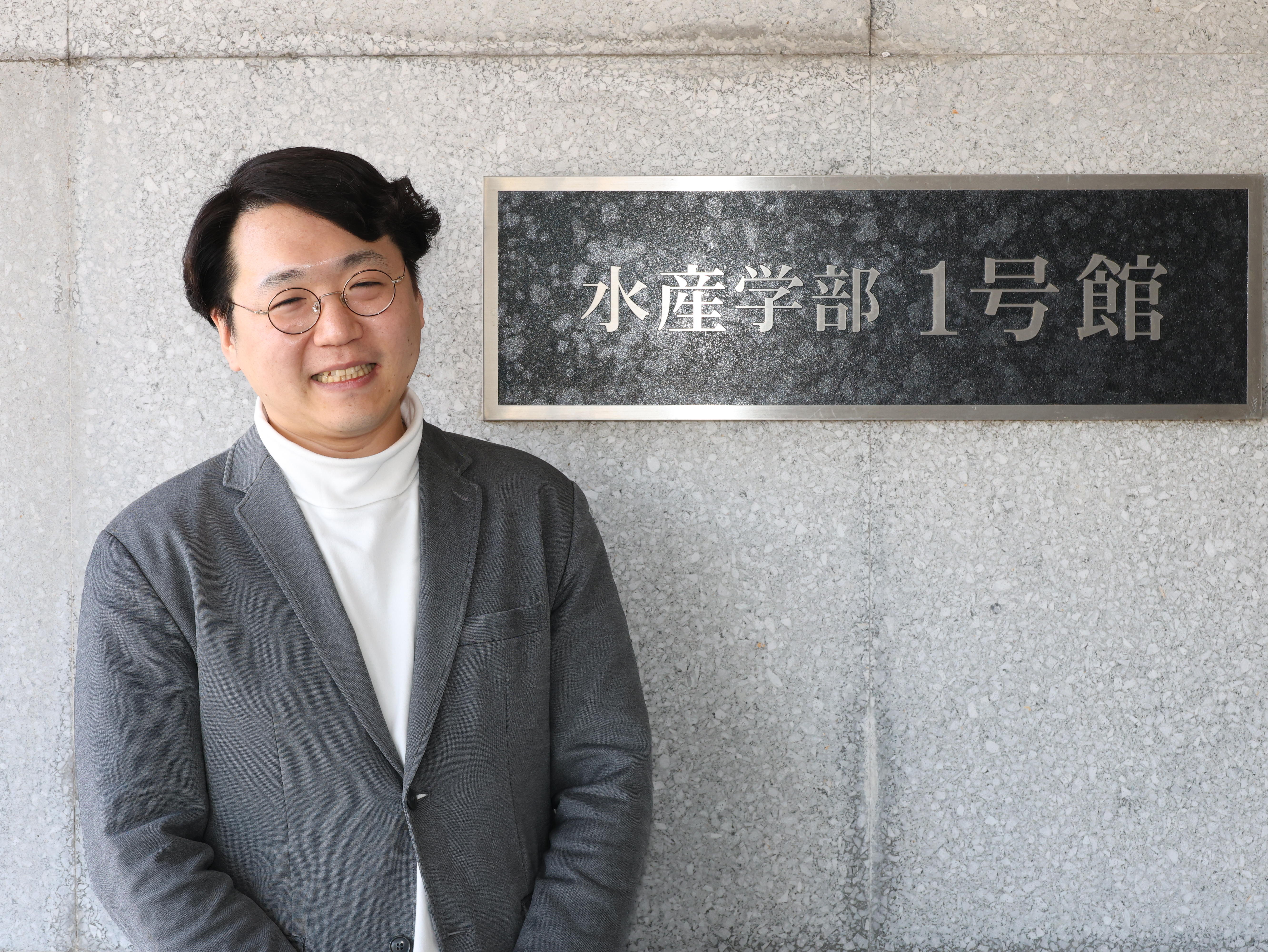私たちの口元に水産物が届くまでの「実はスゴイ」社会構造

皆さんは、水産物を買う時に何を考えますか?せっかく食べるなら、満足を感じられる美味しいものを買いたいと思うのは当然のことですし、食卓を豊かに彩ることができる魚食文化に恵まれているのが日本の強みです。願わくは、こうした魚食文化を未来永劫、謳歌できればと願う方も多いのではないでしょうか。
そんな私たち日本人の口元に美味しい水産物が届くまでの流れは、世界的に見ても非常に複雑で、たくさんの方々の労働によって支えられています。日本で漁業者が水揚げした水産物は一般的に、産地の卸売市場で競売(*1)を行う卸売業者(*2)に販売が委託され、その競売に参加して競って水産物を買っていく仲買人(*3)の手に渡っていきます。仲買人の中には、東京都等の消費地の卸売市場に仕入れた水産物を出荷する方もいます。こうして、産地から消費地に出荷されてきた水産物は、消費地卸売市場の荷受業者(*4)にその販売が委託され、競売等の方法で小売店や飲食店に渡り、最終的に私達の口元に届くのです。多種多様な水産物を刺身品質で食べることができる日本の水産物流通構造には、海外の消費者やビジネスマンも関心を寄せています。
では、こうした多くの人々が関わる水産物の流通構造は、今後も維持できるのでしょうか?この構造を支える人々のお仕事はどのようなもので、どんな課題を抱えているのでしょうか?
水産物流通の現場では何が起きているんだろうか?

私は、水産物流通を担う方々のお仕事の実態や、直面している課題を調査し、日本の水産物流通という社会構造の理解を深める研究をしています。最近では、水産物流通の入り口である産地卸売市場の機能や、そこで水産物を競って買っていく仲買人の実態と課題に着目しています。彼らがいなければ、日本の漁業者が水揚げした水産物には価格がつかず、漁業者は収入を得られません。もちろん、私たちも各地の多種多様な水産物を楽しむことができなくなり、食卓には輸入されたマグロやサーモン等の限られたものしか並ぶことができなくなります。
また、最近では多くの水産現場で、不漁(*5)や魚種の変化が起きています。このような状況に、産地はどのように対応しているのでしょうか?岩手県のとある水産加工業者は、量がまとまって水揚げされない水産物を産地卸売市場で仕入れ、それを人の手でお刺身まで下ろして凍結処理を施す、冷凍刺身の開発を行っています。「生で食べる刺身を凍らせるの?」と驚く方もいらっしゃるかと思いますが、最新の技術で凍結した刺身は、解凍後も生に匹敵する食感を再現できます。そして、お刺身まで下ろすことで、皆さんが家で水産物をさばく手間を省き、手に取りやすい製品に仕上げています。私の研究では、こうした産地の取り組み事例も調査しています。
用語解説
*1 競売とは、産地卸売市場において水産物の価格を決める方法の一つです。有名なセリや入札といった、複数の仲買人同士の競争によって水産物の価格を決める手法が含まれます。
*2 多くの場合、産地卸売市場に水揚げをする漁業者が所属する漁業協同組合が卸売業者として産地卸売市場を開設しています。漁業者から水産物の販売を委託され、仲買人を対象に競売を行い、その結果の売上金額を漁業者に還元する役目を担っています。
*3 産地で小売店を営む方や、加工業を営む方、消費地卸売市場の荷受業者に水産物を出荷することで生計を立てている方等、様々な業種の方が該当します。共通するのは、産地卸売市場の競売に参加する買参権を持っている点です。
*4 消費地卸売市場における卸売業者のことで、日本全国の産地卸売市場から出荷されてくる水産物を消費地卸売市場で受け取り、仲卸業者や売買参加者に競売等を通じて売り渡します。この内、仲卸業者とは消費地卸売市場内に店舗を構える業者で、個人経営の飲食店といった小口需要者に水産物を販売します。売買参加者とは、スーパーマーケットといった量販店で、大量の仕入れを必要とする業者のことを指します。
*5 特定の魚種が獲れなくなる状態を意味します。「サンマが不漁」といった表現をニュースで目にしたことがある方も多いのでないでしょうか。