価値観に再挑戦する政治学

政治は実に広い領域をカバーしています。戦争や国内外の選挙やいろんな政策の分析と言ったイカニモな話から、「私的」問題とされてきたジェンダー領域やLGBTQの領域にいたるまで、政治は深く関わっています。政治不在の領域を何か思いつきますか?ほとんどあがってこないのではないでしょうか。新聞などのメディアや本屋さんをみても政治ものが多いですね。
さて、このようにカバーすべき領域が広い政治学を分ける方法はいくつかあります。一つの分け方を試してみましょう。価値を扱う政治学とそうでないものとにです。価値を扱うとは、例えばデモクラシー(民主制)は他の政治体制に比べて優れているかどうかといった類のものです。実は従来型の古典的な政治学は政治学史(政治理論史)や政治思想史といったもっぱら価値を扱うものでした。ところが、近年の世上では価値判断を嫌い、あるかどうかわからない「中立」が良いとされる風潮があります。この結果、政治科学(ポリティカルサイエンス)という流派が興隆しています。価値判断を排除することで可能な限り研究者の主観をとりのぞくものでいまや主流です。例えば選挙結果の数理データ分析などは典型的です。
それでは旧来からある政治学史や政治思想史などが無為なものになったのかというとそんなことはないと思います。過去にどのような価値が謳われていたのか、それら価値をいかに整理・陳列できるかといった仕事は、今後に価値判断を迫られた際には必要となる情報です。しかも整理・陳列までの学術的な作業は価値判断をせずともできることだからです。この判断の源にある価値観について、今度は「色メガネ」という言葉におきかえてもう少しお話ししましょう。
私の専門は政治史・政治思想史ですが、学べるものを最小限度に表現すれば「色メガネをたくさんもち、選べるようになる」と言うことだと思います。すべての人は「色メガネ」で世界をみているものです。私のような浅学はもちろんそうですし、どんなに学問的に鍛えられていても「色メガネ」をかけた状態です。「存在被拘束性」という言葉があるように人は必ずバイアスをうけており、そのバイアスを通じることによってのみ世界を認識しているわけです。
では、どうしたら世界をより正確に認識できるのでしょうか?さまざまなバイアスを知る、換言すればたくさんの「色メガネ」を理解し、使えるようになればいいわけです。そうすれば「色メガネ」なしに世界を見ることはできなくとも、複数の「色メガネ」で見え方を比較したり、一つの見え方を相対化することができます。政治学は哲学や文化人類学などとともに、バイアスと言うメガネをある程度コントロールできるようになる手法をもっているのです。すなわち政治学は古代ギリシャ哲学の頃から、国家や社会を包み込む考え(=イデオロギー)、あるいは国家や社会を構築する際のデザイン案(=政治思想)などを多く分析し検討してきたデータの蓄積をもっています。まさに国家や社会に関する考えやデザイン案のデータベースだとも言えるのです。
歴史的な国際政治論研究
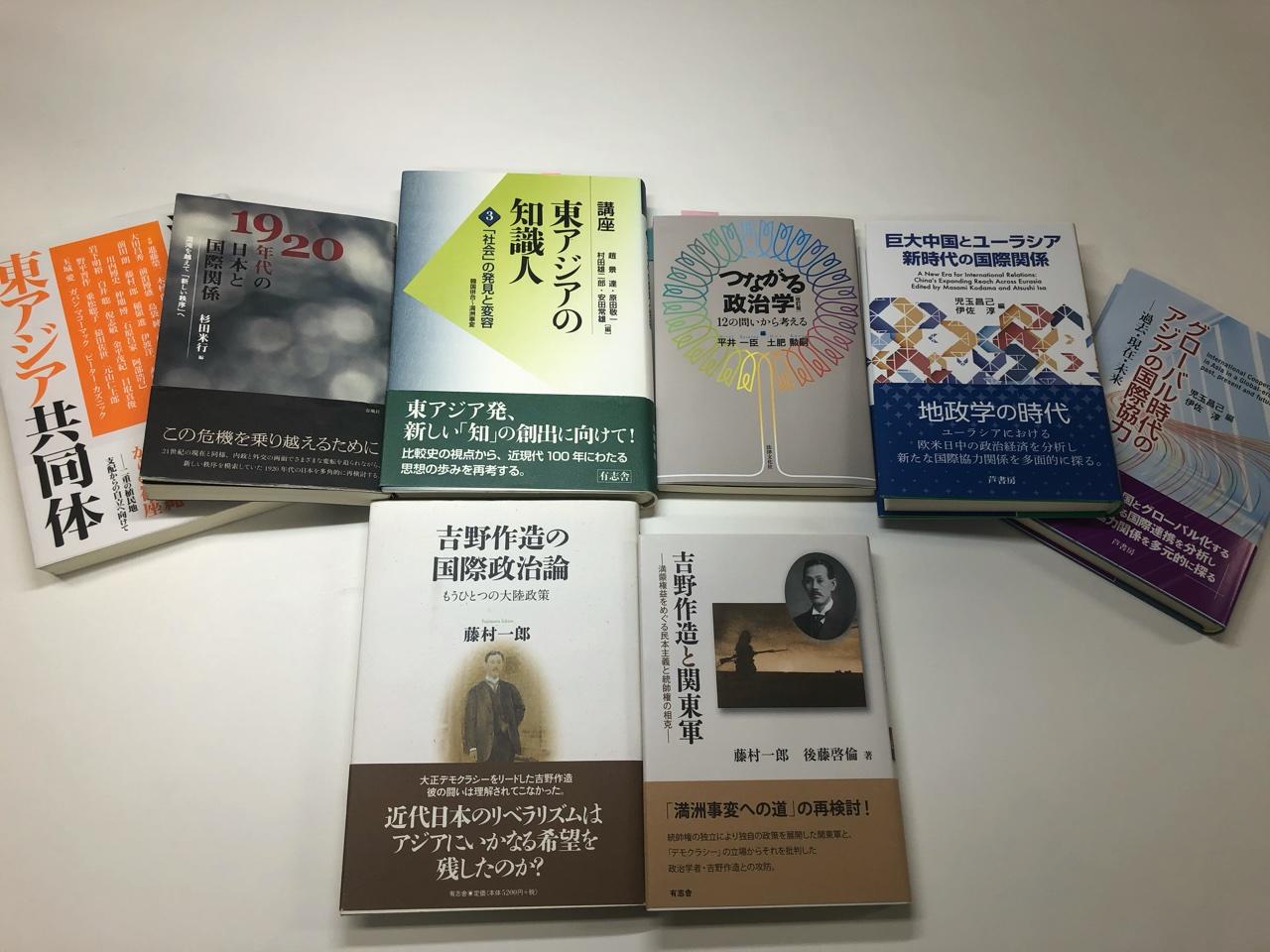
さて、歴史は政治学にとって分析対象として必要不可欠です。なぜでしょうか?例えばあなたの友人が恋人とつかみあいのケンカをしているとしましょう。つかみあっている様子では、友人が強く恋人は一方的にやられており、友人が悪く見えてしまいます。しかしケンカにいたった経緯を双方から聞いてみると、必ずしもあなたの友人が全面的に悪いわけでもないことが見えてきたとします。国際政治においても、国内政治においても同様のことが言えます。経緯、すなわち歴史を知らないまま、今だけを切り取って政治を論じることは非常に危険なことなのです。また歴史を軽視することはこれからの未来へ向けた判断を見誤ることにもつながりかねません。「色メガネ」の整理・陳列には「色メガネ」が生み出された背景を必要とするのです。
ですから私の研究は、政治史や政治思想史といった歴史学的手法をとります。歴史的にどのような政治的バイアスが存在していたかを検討していると言ってもいいでしょう。私は戦前・戦中・戦後直後の日本の知識人の国際政治の見方を研究してきました。なかでも時間をかけたのは、帝大の政治学の教授だった吉野作造で、私の博士論文は「吉野作造の国際政治論」でした。知識人を研究対象とした理由は、かつての知識人は理論的に整理された政治思想をもち、国際的に高度な知的交流をもち、国内において言論人として大きな影響力をもっていたからです。吉野作造は「大正デモクラシー」期の自由とデモクラシー(民本主義)の旗手でした。国際政治をどう見たのか、と言う点にこだわった理由は、当時、国際政治領域についての研究が立ち遅れていたことにくわえ、国内政治とは全く異なるロジックを持つ国際政治について検討することこそ、吉野作造の思想に最接近することになるだろうと考えたからでした。
あなたはどんなバイアスで世界を見ていますか?同時代の日本はどうですか?あの時代の世界は?一緒に楽しく研究できるといいですね。
用語解説
「存在被拘束性」とはどんな思想も知識や観念も、歴史的・社会的な文脈により条件付けられ、立場や時間に拘束されているということ。
「バイアス」をここでは先入観や思い込みといった意味で使用している。
「イデオロギー」について、G.ルカーチやK.マンハイム、そしてL.アルチュセールらの諸説を参考にしていただきたいが、一言にすれば、ある社会や政治の中の「存在に拘束された思考」であり、しばしば政治権力によって知らず知らずのうちに教え込まれたものをさす。
「吉野作造」(1878-1933)帝大で2番目の政治学担当者。「民本主義」(≒デモクラシー)の主唱者。1919年の中国の五四運動や朝鮮の三一独立運動を擁護したことでも知られる。
「国際政治論研究」対象者の国際政治についての秩序原理や構成要素をどのように捉えるのかといった部分を核としつつ、国際組織への認識や外交政策、国家間関係のあり方についての言説を分析する研究。歴史観や人間観などまでに深掘りすれば政治思想研究と区別する必要はなくなる。
































































































































