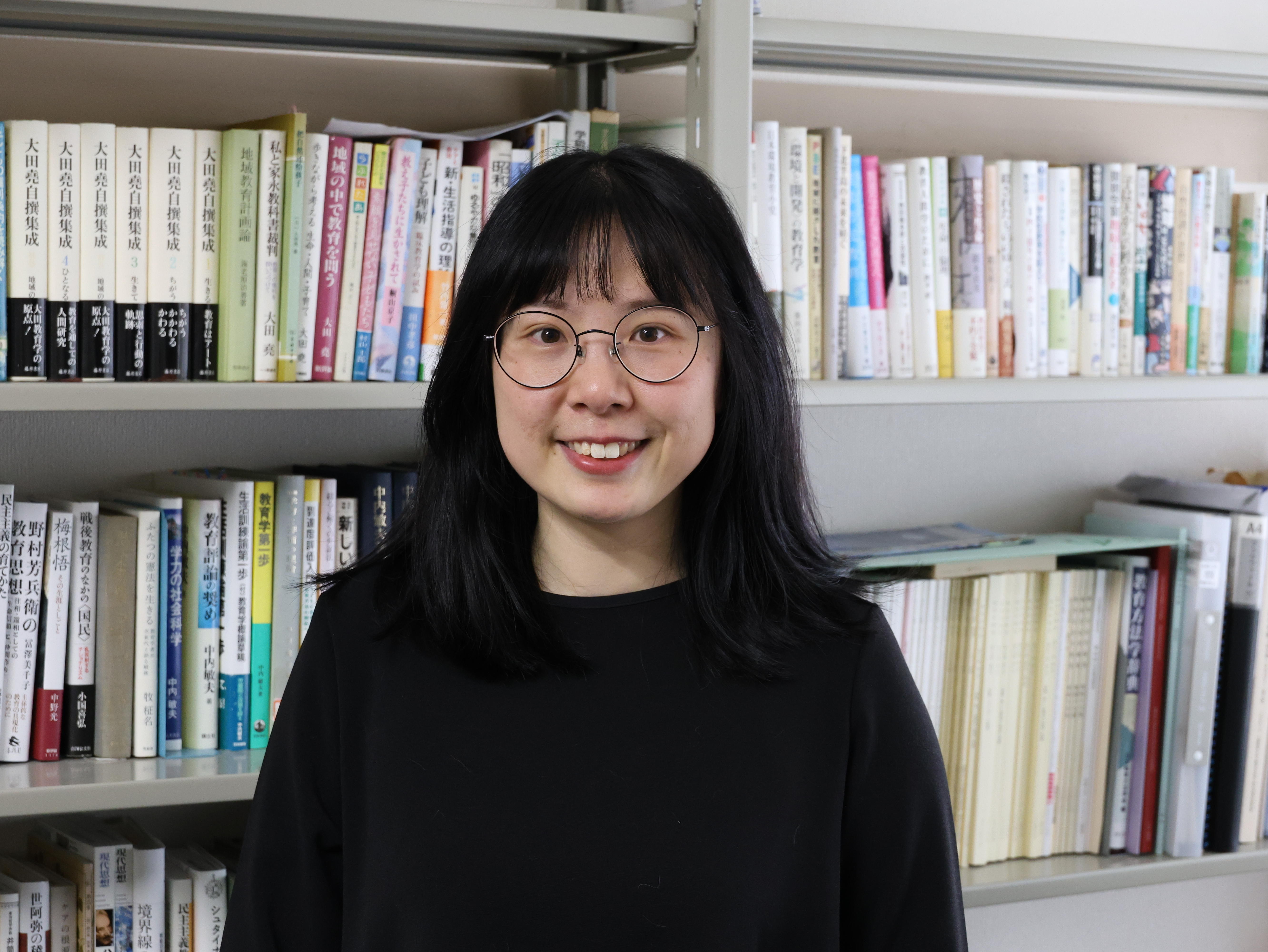日本特有の環境教育の蓄積への着目

2000年代以降、環境教育に関する研究では「持続可能な開発のための教育(ESD):Education for Sustainable Development)」が2002年に提案され、2015年には「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」が採択されました。これらの国際的な枠組みが中心となり、多くの学校でさまざまな環境教育実践が行われるようになっています。しかし、日本の歴史的社会的文脈を踏まえて展開された「ボトムアップ」型の環境教育の理論と実践が、だんだんと忘れられてきています。また、環境に関する知識やテーマだけに注目が集まりやすく、子どもや教師、保護者、学校、地域など教育に関わる者にとって、その意味が十分に考えられないまま進められる場合があるという問題も指摘されています。一方、日本特有の環境教育の蓄積においては、子どもの成長を大切にし、地域の課題や状況に向き合いながら、教育学の理論と一緒に発展してきた独自の環境教育論があります。私の研究では、こうした日本ならではの環境教育に注目し、それを深く探っていきたいと考えています。
教育学者の環境教育論を読み解き、構造化する

私の研究では、1960年代から1990年代にかけて、日本の教師たちが公害や開発問題に目を向け、地域の課題に取り組んできた教育活動と、それをもとに教育の理論を作り上げた研究者たちに注目しています。この研究を通じて、日本特有の環境教育の理論と実践を明らかにしようとしています。現在は、特に藤岡貞彦(1935- )、中内敏夫(1930-2016)、大田堯(1918-2018)の所論を、日本における環境教育の三つのアプローチとして対象化し、彼らが高く評価していた教育実践を手がかりとすることで、各アプローチの特質、意義と課題、および、三つのアプローチの関係を明らかにすることを目指しています。現段階の結論として、三つのアプローチはそれぞれ、地域の現実的な課題に取り組むことで、教育の役割を問い直す「社会批判的アプローチ」、地域の自然や社会に目を向けることで、教育の内容や方法を考え直す「文化的アプローチ」、地域で人や自然と豊かに関わることを大切にし、教育の本質を問い直す「生命的アプローチ」になります。私は、これらのアプローチの関係性を解き明かし、日本の環境教育がどのように理論と実践の両方で発展してきたかを整理し、地域に根ざす環境教育のあり方にヒントを示したいと思います。
用語解説
*1 藤岡貞彦は公害教育実践の可能性にいち早く着目し、その理論化を試みた教育学者です。1960年代後半に藤岡は、社会教育の立場から住民運動における学習活動に着目するとともに、それが学校教育にもたらす変化にも目を向け、公害と教育の関係について広範に論じるようになりました。
*2 中内敏夫は、1970年代半ばから公害や開発問題に取り組む教育実践に着目し、地域社会の変化が学校の教育課程編成に影響を与えた教育実践としてこれらの実践を価値づけ、教育課程論を展開しました。
*3 大田堯は、1980年代後半以降、環境問題と学校の荒廃、子どもの生き方の問題を一体的に捉えることで、環境教育の主張を展開するようになりました。